���̃N�C�Y�̃q���g
-
�q���g�m��Ȃ���
���̃N�C�Y�̎Q���ҁi3�l�j
�W�������E�L�[���[�h
�g�їp�y�[�W

�g�ѓd�b��QR�R�[�h�ǂݎ��@�\�ł��̃y�[�W�������܂��B
�L��

�L��
�L��
�N�C�Y�嗤�֘A����
|
|
�Q���^�i�]�g�L�T�C�g�w�N�C�Y�嗤�x�ŁA�]�g�����ǂ����I |
@quiz_tairiku������t�H���[ |


|

|
 �c�C�[�g
�c�C�[�g
|
 ���ʎ��� ���ʎ���
��Փx�F���� �@

�ߑO�Z���̓��̏o�A���̎����Ȃ��̉e�͂��傤�ǐ��̕����ɐL�тĂ��܂�
������Ԃ����đ��̍��ɍs���A�����炷���ɂ܂��Ԃ����đ��̍��ɍs���A�Ƃ������Ƃ��ߌ�Z���̓��̓���܂ŌJ��Ԃ��܂� �����������ɁA���̍��ł̂��Ȃ��̉e�̐L�тĂ�������͂��傤�LJ@���A�A�k�A�B���A�C���A�D��A�E�k�ʼne�̒����͑S�ČߑO�Z���̉e�Ɠ����ł��� ���̓��̈ړ��������ŒZ�o�H�ɂȂ�悤�ɇ@�`�E�̍��̏��Ԃ���ёւ��ĉ����� ���n�������S�ȋ��̂Ƃ��A�C��͖������܂�
|



�������t��H�Ȃ獡����n�_��ԓ������̂`�n�_�Ƃ��āA�ߑO�Z���ɑ��z���^��ɗ���n�_�́A
�`�n�_����ԓ��̉~���𓌂Ɏl���̈�ړ������a�n�_�ł� ��\�l���ԂɈ��n�������]����̂ŁA���̏o�̌ߑO�Z��������̓���̌ߌ�Z���̏\�ԂŔ������]���܂��B ���̏ꍇ�A�ԓ����\�l���Ԃ̎��v�ƍl���A�w���A�x�������Ԃő���܂��B 

���q�̎q�L�̕��ŁA���X�ł��Ȃ������̂ł�����ŁB
�l�A���\����̍����D���ł���B ������ǁA�Ȃ������c�{�����Ă���̂� �l������������܂��B ���Ȃ݂ɂ��̖����l���� ���Ԃ�����Ƃ��͍l���Ă���̂ŁA�܂��܂��҂��ĂĂ���������  

��u����
���肪�Ƃ��������܂�  ������肪�q�ϓI�Ɍ��Đ������ĂȂ�������ǂ����悤 �ŋ߂����������l���Ă��ł����ǂ����̂��o���܂���  ���𓊍e���Ă��������̓��[���h�J�b�v�ϐ��e�e�P�Q�Ȃǂ����Ă��Ċ������܂��� �F�X�l�����̂ŁA�������C�ɖ����ɔ��U�����C�����܂��B 

���������n�߂�O�Ɉȉ��̂��Ƃ����肵�܂�
�E���Ԃ͍ŏ��ɂ������̎��Ԃ��g�����̂Ƃ��A�����͍l�����Ȃ� �E�Q���Ԃ��ƂɁu���v�́u���v��K���z��������̂Ƃ��� �i�����̒n���ɂ��̂悤�ȓ��ٓ_��T���w�͂͂��Ȃ��j �E�G�߂��t���H�Ɖ��肷�� �e�̏����ɂ������n�_��T������ɁA���̒n�_�Ԃ̋������ŏ�������K�v������܂� ���āA�l�̍ŏ��ɍl�����ł͐ԓ��������̐l�������܂��B �܂��Q���Ԃ��Ƃɑ��z�̓쒆����n�_�ɖ��O��t���܂� �U���ɑ��z�̓쒆����n�_�FA �W���ɑ��z�̓쒆����n�_�FB 10���ɑ��z�̓쒆����n�_�FC 12���ɑ��z�̓쒆����n�_�FD 14���ɑ��z�̓쒆����n�_�FE 16���ɑ��z�̓쒆����n�_�FF 18���ɑ��z�̓쒆����n�_�FG ������ (0)���A�@���A�A�k�A�B���A�C���A�D��A�E�k�Ȃ̂� ���̐l�̈ʒu�́A �U���FA���������i�e�͂�����Ɛ��j �W���FB���������i�e�͂�����Ɠ��j 10���FC��������i�e�͂�����Ɩk�j 12���FD���������i�e�͂�����Ɠ��j 14���FE���������i�e�͂�����Ɛ��j 16���FF�������k�i�e�͂�����Ɠ�j 18���FG��������i�e�͂�����Ɩk�j ���������āA�ړ��o�H��ABCDEFG�̏��Œn�����i20000�L���j�ړ������A�Ƃ����̂����� ���Ԃ��@�A�B�C�D�E�̂܂܂ł��B 

���������l���������e���Ă����܂��B
���̐l�͖k�ɓ_�ɂ��܂����B �k�ɓ_��^�ォ�猩��Ƃ��ꂼ��̕��ʁi���_�I�Ɍ����ȕ��ʁj�� �E�� �Q���Q ���_�� �Q���Q �E�k �Q���Q ���_�� �Q���Q �E�� �Q���Q ���_�� �Q���Q �E�� �Q���Q ���_�� �Q���Q �ƂȂ�܂��B�܂肱�̐}�̍������瑾�z�̌����������Ƃ���� ���� �����_ ���� �k�ɓ_�̍��ɂ���A�e�͖k�� �k�ɓ_�̉E�ɂ���A�e�͓�� �k�ɓ_�̏�ɂ���A�e�͐��� �k�ɓ_�̉��ɂ���A�e�͓��� �L�т邱�ƂɂȂ�܂��B �e�̏�����(0)���A�@���A�A�k�A�B���A�C���A�D��A�E�k�ł����A �k�ɓ_�𒆐S�Ƃ��Đ����������Ƃł��̏��������܂� �Ȃɂ�����������C����ł���̂ł��̐l�͓������ɍς݂܂�  

��u����
�ƂĂ��ǂ��l�����ł�  �ł����̖��ɂ͂���d�|���������āA �u�ߑO�Z���̓��̏o�A���̎����Ȃ��̉e�͂��傤�ǐ��̕����ɐL�тĂ���v �u�e�̒����͑S�ČߑO�Z���̉e�Ɠ����v ���̏o�̎��͑��z�͓쒆�ɂ͖�����ł��B�i���̎��̑��z�̈ʒu���d�v�j �e�̒������`�`�f�̂ǂ̒n�_�ł����̏o�̎��Ɠ��� �A�Ƃ����̂��d�v�ł� ����Ɩk�ɓ_���o�Ă��܂�  

�H���A�t���ɁA�k�ɓ_�Ɂu���̏o�v�͂Ȃ��B
�i�n�����������o�����܂܂�����j �u���̏o�v�Ƃ����̂́A�n�������瑾�z�̒[���o�Ă��邱�Ƃ������܂��ˁB 

ITEMAE����
����͍l���ĂȂ�����  �ł������̖��Ȃ炬�肬����v�ł� �u�Z���ɑ��z���쒆���Ă���`�n�_���炱�̎����鍑�܂ł̋����v ���a�n�_�A�b�n�_�c���炻�̎����鍑�̋����Ȃ̂� ���̏o�͂`�̎��݂̂ł� 

ITEMAE���w�E�ǂ���
 �܂�No.5�̉͑S�R���߂ł��ˁB ���Ƃ͉e�̒�������̏o���̒����i���قځ��H�j�ƂȂ�����Œn�����삯����ƁB ���x�͈ʒu���w���������߂ɒn�������v�Ɍ����Ă܂��B �n����k�ɑ����猩���~�`�Œ��S�͖k�ɁA�~���͐ԓ��B ��ɂP�Q���̖ڐ��肪����Ƃ��܂��傤�B �n���͖k�ɂ��猩�Ĕ����v���Ȃ̂� �ŏ��̎��_�łX���������瑾�z�������Ă�Ƃ���� ���z�̍��������ɂ��鎞�v�̖ڐ���͓Ԃ��ƂɂX���P�O���P�P���E�E�E���R�ƈڂ�ς���Ă����܂��B ����܂��� A�n�_�̎����F���z�̍����ڐ���̐����F�n�_�̖ڐ���ʒu �̂悤�ɏ����Ă����� 0)�U���F�X�F��������̏o����ʒu�i�{�R�j���P�Q �@�W���F10�F���ɓ��v����ʒu�i�|�R�j���V �A10���F11�F��̒n�����ɑ��z������ʒu���k�ɓ_ �B12���F12�F���ɓ��v����ʒu�i�|�R�j���X �C14���F�P�F���ɓ��v����ʒu�i�{�R�j���S �D16���F�Q�F�k�̒n�����ɑ��z���݂�ʒu����ɓ_ �E18���F�R�F��̒n�����ɑ��z���݂�ʒu���k�ɓ_ �����āA�ړ��������ŒZ�ɂȂ�̂� �D[or �A�E]���C���@���B��(0)���A�E[or �D] �����ǂ��ł��傤�H�����ꑧ����  

��u����
�k�ɓ_����n�������āA���̏o���A�\�����Ɏ���������Ƃ�����A���z�͉��������ɂ���̂����|�C���g�ł� ���̓��莞�i�ߌ�Z���j�ɑ��z���ǂ������l����ƕ�����܂� �i�n���͈����]������j 

�����ă`�������W�B���҂������Ă���܂���B
������A���ʂ̎��v�i����P�Q���ԁj�̗�����������g���܂��B �܂��A �y���z����������F���̏o�����F���̓������z �͂Q���Ԃ��Ƃ� �y�H�F�K�F�E�z �y�I�F�@�F�F�z �y�J�F�A�F�G�z �y�K�F�B�F�H�z �y�@�F�C�F�I�z �y�A�F�D�F�J�z �y�B�F�E�F�K�z ���ɉe�̒����ł����A���̏o���̉e�́��ł��B �O�ł͐ԓ��サ���l���Ȃ������̂��~�X�ŁA �y���z�̂�������F�e���Ԃʼne�̒��������ɂȂ�ʒu�̏����z �͂Q���Ԃ��Ƃ� �y�H�F�K�k�E������ԉ~��z �y�I�F�@�k�F������ԉ~��z �y�J�F�A�k�G������ԉ~��z �y�K�F�B�k�H������ԉ~��z �y�@�F�C�k�I������ԉ~��z �y�A�F�D�k�J������ԉ~��z �y�B�F�E�k�K������ԉ~��z �̂悤�ɂȂ�܂��B����ɁA�e�̕��p����������ƁA �y���z�̂�������F�����̉e�̕����F�n�_�̂���ʒu�z �͓Ԃ��Ƃ� �y�H�F���F�K�kor�E��̉~�ʏ�z �y�I�F���F�k�For��@�̉~�ʏ�z �y�J�F�k�F��ɓ_��̂݁z �y�K�F���F�k�Hor��B�̉~�ʏ�z �y�@�F���F�C�kor�I��̉~�ʏ�z �y�A�F��F�k�ɓ_��̂݁z �y�B�F�k�F��ɓ_��̂݁z �ƂȂ�܂��B�Ō�ɂ����̏������ŒZ�ɂ���_�����肵�Ă�����ł��ˁB �ӂ��`�B��ς����ł����A��ɓ_�Ɩk�ɓ_��ɂ��邩��ɂ͔����͂���̂ł��傤�� ��x�݂��܂��B���l����̂ɃC�b�p�C�Ń��X���Ă܂���ł������A ���\����̓T�b�J�[�ϐ��Q�[�������ł��ˁB�l���V�������Ƃ����ĐF�X�h������ �i��������Ƃ����̂ł��傤���j�F�X�r�����Ȃ��l���������т܂����A���̂܂܃{�[���Ƃ��Ă܂����B �N�C�Y���Y�ɂ��̗͂������ăJ�^�`���Ă݂悤���ȂƎv���܂����B �����A������猩���Ă��������ˁ` 

���[��
�l�����͂����Ă��ł����ǁA���͂̉��߂̈Ⴂ���c ����ς肱�̕ӂ��u�q�ϓI�Ɍ��Đ������ĂȂ�������v  ����܂�l�������ďd�ׂɂȂ�ƈ����̂ŁA�����������������������ł��ˁc �l���鎖���̂��̂͗ǂ���ł����ǖ��͈���Ƃ����邩�� �{�[���Ƃ���̂͂����ł��� ����Ȃ��l���������ē������Ă���ł� �����͐̂���������܂���ł������A�ŋ߂����Ďd�����Ў�ԂɁA�l���ă{�[���Ƃ��Ă܂� ��{�I�ɃQ�[���ł����ł����܂����A�N�C�Y�쐬��N�C�Y�����ȂNJ܂߂Ĉ�`���͎����̃y�[�X�Ő�O������A�ʂ̎��������b�B�ɂȂ鎖���n�߂܂� ���G�Ȏ������I�Ȃ��Ƃ��o���܂��ǁA�v�l���J�e�S���[�ɑ����Ȃ��悤�ɂ��Ă���̂ŁA�h�����ďW�������牽�ƂȂ��N�C�Y�����Ă��肵�܂� �N�C�Y�쐬�ł����ł��`���ƍl����Ƃ��̂��������o���Ȃ��Ȃ�܂� �Ȃ�ׂ��X�g���X�������Ȃ��悤�Ɏ��R�Ɋy���肵�Ă���A���̊Ԃɂ��b�B�������Ƃ��o����悤�ɂȂ��Ă��� �i�����Q�`�R�N�͂قڂ���Ȋ����j �H�v�͎����������ł����ǁA����������ȏ�������̂ŏ����ڋ�����  �����Ƃ��v���O���}�[�Ȃǂ̐��]�����߂��Ă���l�ɂ͂����߂��܂��ǁA��L���y����ŐF�X�l�������l��  

�l�A��ώ�L�����Ȃ̂ʼn��ł�����ł��S�������Ă���킯�ł��B�N�C�Y�̒��ł�
�E�菇�߂ΕK���������o�� �E�m��������Ή����� �Ƃ���������������������̂��Ȃ��̂��킩��Ȃ����ɔR���Ă��܂��܂��B ��{����ʂ����A�V�����g�g�݂������Ă����Ⴄ�����邱�ƂŁA�o���o���������p�[�c�����R�ƕ��u�Ԃ̉x�тł��ˁB ���\����̖��́A��蕶���u�V���v���v�ɐ�������Ă��đz���͂��h�����܂��B���R�x�������B ������������A�l���Ђ����邻�́u�V���v���v�������������u�q�ϓI�ɐ�������v���߂� �������ӂ邢���Ƃ��Ă���̂�������܂���ˁB �Ⴆ��Ȃ�� �uA�~B���Q�ƂȂ�A�AB�̑g���Ȃ����v�Ƃ����N�C�Y�ł��B ���\����͓������uA=�P�CB=�Q�v�Ɗm�M����X�g�[���[�������ďo�肷��̂ł����A ���̑O��������ӎ����܂���B�ł��A������ɂ���ɂ� �uA,B�͐����v �uA,B�͂O���傫���v �uA��B��菬�����v �̂R�������K�v�ł��ˁB �����ŁA���̗��z�̉͂��̉\����ԗ����邱�ƂȂ�ł��B ���̏ꍇ����xy���������Ĕ����̑o�Ȑ��������Ƃ��B ���������̃V���v���ȏo��X�^�C�����䖳���ɂȂ�܂����R�`���C�X�p�ӂ��Ă݂܂����B �E���̖��K�͂ŃN�C�Y�Ƃ��Đ���������Ȃ� ���ɂ��璷�����������āA���낢��ݒ�𑝂₷�ƃN�C�Y�̈Ӑ}���]���Ƃ���Ȃ��`����� �l���Ă����ɉ҂��݂��т���� �E�V���v�������ێ��������Ȃ� ���̋K�͂��������������Ă݂�ƁA�S�e�����݂₷���Ȃ� �E��K�͂����G�̂܂܂��� �l������������ɂ����Ⴂ�܂�  

���ł����킵�Ă���Ƃ��̉ߒ��Ŏ��R�Ȏv�l���o����A
����𖡂키���߂ɐF�X�Ȃ��Ƃɒ��킷��̂���  ���ɑ���ӌ��͎^�ۗ��_�ǂ�����������炢���̃X�e�b�v�ւ̎Q�l�ɂȂ�܂� �N�C�Y������Ă��l�Ɍ����Ȃ��Ƃǂ��������b�Ɗ��� �����쐬�ւ̈ӗ~����胉�C�����Ȃ��Ƒʍ삵���o���Ȃ��̂ŁA �i���G�����A���ς̗]�n����A�o���������A�Ȃǂ̗��R�łV�O�`�W�O��قǂ̃N�C�Y����������j ���Ԃ�u���ĐF�X�ƒ��킵����܂����܂�  ���̎��͋L���͂Ȃǂ̋@�\��m�������o���l��M�ӂ��K�v���Ǝv���܂��� �i�c�����Ɠ������炢�̔M�ӁA�D��S�������Ɓj �ł��g�̊댯���뜜���Ȃ�����A�l�͗��R�������������Ɠ����Ȃ������肵�܂� �ŁA���R�T���̗������Ă܂��i�����⏑�ЂŁj �ȑO�́u�V�ˁv�u�_���v�ȂǂŌ������āu�����`�I���̒�����Ȑl�������̂��`�v�Ǝm�C�����߂܂��� �̐l�Ƃ͎��ۂ́u���O�ꂽ�w�͉Ɓv�ł����āA�u�V�ˁv�Ƃ͌����Ȃ��̂ł́H�Ǝv���܂����A ���̐l�B�̍s���A�l�����͖͕킷�鉿�l������܂��� 

�V�A�W�O����̎r�̏�ɂ��z���Ă�����肽���Ȃ�ł��ˁB
�l�̎�������͌����Ȃ����̂���ł��B�ʂ�Ő�������Ă������ �ł͂ł́A����y���݂ɂ��Ă܂�  

ITEMAE����
���̏o�Ɋւ��� ����͊ԈႢ�B���̏o�͑��z�������ł��n�����������o�����u�ԁA���̓���͑��z�����S�ɉB�ꂽ�u�Ԃ̎�����������̏o�����̓��������B 

�����ł����A���炩�ɖ�蕶�ɕs��������̂ŁA
���̏�Ԃ��Ɛ����ƌ�������̂������ł�  �����܂��� �����܂����iNo.13 �̕ԐM�ŁA�v���`���Ă����N�C�Y�Ǝ��ۂ̃N�C�Y�̐������̈Ⴂ�ɋC�t���܂����j �u�ߑO�Z���̓��̏o�A���̎��`�n�_�ł͂��Ȃ��̉e�͂��傤�ǐ��̕����ɐL�тĂ��܂� ������Ԃ����đ��̍��ɍs���A�����炷���ɂ܂��Ԃ����đ��̍��ɍs���A�Ƃ������Ƃ��`�n�_�œ��̓���ɂȂ�ߌ�Z���܂ŌJ��Ԃ��܂��v �ƌ������ɏC������Ζ�肪�������܂� �Q�S���ԂŒn���͈�]���A���̏o������̓���܂ł̎��Ԃ��P�Q���Ԃł��̂ŁA �n����k�ɓ_�𒆐S�Ɍ��āA�ԓ��̉~�ɖk�ɓ_��ʂ钼���a�Ƃ��Ĉ����ƁA �`�n�_�͉E�̐}�u�Ɓv�̈�ԏ�̈ʒu�ł� ���̏o�̎��̑��z�̈ʒu�͒����̍����A���̓���͒����̉E���ƂȂ�܂� �u�e�̒����͑��̍��ł��ߑO�Z���̉e�̒����Ɠ����v�A�Ƃ����̂́u���z�̈ʒu���炻�̎��ɋ���n�_�܂ł̋����������v �Ɖ��߂��A���̋����͉E�̐}�u�Ɓv�̒ʂ�A���̏o�̎��̑��z�̈ʒu�Ƃ`�n�_�̒����̐ԓ��P�^�S���̒����ł� �ԓ����Q�S���Ԃ̎��v�Ƃ��A���̏o�̎��̑��z�̈ʒu���U���Ƃ��܂� �܂��`�n�_�͐��ɉe���L�тĂ���̂ŁA�P�^�S���U�^�Q�S�ő��z�̈ʒu����Z���Ԑ��́A�P�Q�������ɋ��܂� ���z�̈ʒu���W���̇@�ł͓��Ȃ̂ŁA�Z���ԓ��̂Q�������ł� ���ɁA���z�̈ʒu���P�O���̇A�ł͖k�ŁA�Z���Ԗk�̖k�ɓ_�Ƃ���Ɖe����ɐL�т�̂ŁA�t�ɘZ���ԓ�̓�ɓ_�ł� �����悤�ɁA�B�i���z�P�Q���j�͂U�������A�C�i���z�P�S���j�͂Q�Q�������A �D�i���z�P�U���j�͖k�ɓ_�A�E�i���z�P�W���j�ł͓�ɓ_�����̎��_�ŋ���ʒu�ł��B �ŒZ�����͉��ʂ肩����A�Ⴆ�� �`�n�_�P�Q���������A��ɓ_�i�E��ɓ_�j���C�Q�Q���������@�Q���������B�U���������D�k�ɓ_�A�Ȃǂł� �����̗\���ł͉Ă�~�̎����͐������Ȃ��A�͂���������ł����悭�悭�l����Ɛ�������ꍇ������܂��B ��蕶���u�����͏t�^�������ŁA�c�v�ȂǂŎn�߂Ȃ��Ƃ��Ȃ�ʓ|�Ȏ��ɂȂ� |
|
���₢���킹 | �y�����N�C�Y�̔��M��n�I http://quiz-tairiku.com/ |
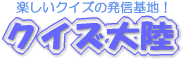

 �_���p�Y��
�_���p�Y�� �_���p�Y��
�_���p�Y��