このクイズのヒント
-
ヒント知らないよ
このクイズの参加者(15人)
広告

広告
広告
広告
広告
広告
広告
広告
広告
クイズ大陸関連書籍


|

|
 ツイート
ツイート
|
 右から左へ書くのは・・・ 右から左へ書くのは・・・
難易度:★★★

某出題にての話題。
左利きの人は、文字が左から右にならんでいて書きにくい。 そもそも、文字自体が右利き用に出来ている・・・ という不便にさらされています。 (昔、右から左の横書き看板がありましたが、むちゃくちゃ書きにくいはず) ところで、こんな疑問を持った方はいらっしゃいませんか? 「国語の縦書きは、なんで右から左なんだ。 鉛筆で書き進んでいったら、右手が真っ黒になるじゃないか」 文字が「→」むきなのに、行が「←」むきに並んでいるのはなぜでしょうか? 考えられる理由をお書きください。 キーワードで「かってに君」が反応します。 >>16 に「おまけ」あり。 
|

|
ITEMAE
本質的に、おしい

ITEMAE
誰が始めたんだ〜

ITEMAE
根本的にソレですが
書くときの不便がなかったか・・? という意味で、おしい! 審判! デッドボールだよ、ここに・・
ITEMAE
元祖は、どっちから書いても手は汚れなかった時代に・・・

昔は筆だった。右手は浮かして書くので、右から書いても、手は汚れない。左手は紙を持ったり押さえたりする。左から書くと、左手が汚れる。


こういうことにしておこう。

ITEMAE
 ↑の回答と同じ ↑の回答と同じ
ITEMAE
のちほど公開しましょう。

ITEMAE
たしかに、時代は、中国から始まります。

ITEMAE
むかしの中国で、「右」から行がはじまりました。

ITEMAE
筆はつかいますね。

ITEMAE
>>1の「おしい」。
ITEMAE
 
ITEMAE
右ききが始めたと思います。
 左手の使い方はポイントです。 
ITEMAE
たしかに、そんなことがあるでしょうが、
「筆」をつかう時代に「右」から始めるメリットが。 
ITEMAE
さらに時代は・・・



もちろん、最初に右から書いた人が「こういう理由で」と解説しているわけでないので、
「これが正解だ」ということを私が断定することは間違いなのですが、 歴史をひも解いて、 「そういえば・・  」 というキーワードが出てくるはずです。 」 というキーワードが出てくるはずです。ついでに、おまけ。 アラビア文字というのは、文字そのものが「右から左」だそうです。 (私は書いたことがない  ) )これも、理由があるそうです。 さて?
ITEMAE
当然、墨は想定ずみ。

ITEMAE
じつは、書くときは巻いてません。

ITEMAE
書いてから、紙をつなげて巻物にします。
 時代はもっと・・・ 時代はもっと・・・ 
ITEMAE
中国では、トイレ紙のこと。

人間は大半の人の心臓は左にあるから無意識に左に傾く、というのを聞いたことがあるのですが、関係なさそうですね。


こんばんは
 まずはこんなんで 
ITEMAE
「左寄り」であって、「左側」にあるわけではありませんね。
ITEMAE
書くときには、まだ「巻き癖」はついてないですね。
書いた紙を継いで巻物にします。 ふつう。  ちなみに、私は「博物館学芸員資格」を(単位だけ)持ってます 
ITEMAE
そういうことです。
 なお、「書くとき」の左手の使い方もあります。 なお、「書くとき」の左手の使い方もあります。
巻いていなくても、やっぱり毛筆なら手で押さえていないと……。右から左に書き進まないと、墨液が乾くまで、1行ずつしか書き進むことができない。


こだわる
 
ITEMAE
じつに「おしい」ポイントあり。

ITEMAE
社会式株

ITEMAE
 ← ← ← ← ← ← 
ITEMAE
筆は使います。

ITEMAE
単語だけで「かってに君」でした。
書くときも・・。 
字は左から右へ書く。紙にはその方向に引っ張る力が働く。左側が濡れていると、破れやすい。


力学的な理由
 ↓昔は左→右の横書きはありませんでしたので
ITEMAE
横書きするときは・・・

ITEMAE
 で、書のほうは・・・ で、書のほうは・・・ 
ITEMAE
書くほうの都合と、読むほうの都合がありますね。

ITEMAE
「和服」より、歴史は古いはず

ITEMAE
文鎮のほうが、歴史は新しい

毛筆以前・・・。
石板や木片に刻む場合に 左側が未加工なほうが扱いやすかったのかも? アラビア文字は・・・? 宗教的な理由とかありそう。偏見。 

ワカラン
 。書くとき基準。 。書くとき基準。
ITEMAE
「宗教」のほうが歴史は浅いと思います
 何をもって「宗教」というかはともかく。
ITEMAE
昔の日本では、「左」のほうが偉かった
 格上 左大臣 右大臣
ITEMAE
じつは、使ってます。



おまけ問題。 アラビア文字の「左むき」起源。
石板に文字を刻むのに、 左手でノミを持ち、右手のハンマーで打つ と、 「右から左」に進むことになります。 という意味で、>>35おしい  じつは、以前、「水族館」の学芸員の資格をとるのに、 (「博物館学芸員」そのものの資格は、水族館も美術館も同じなので、) 文系の学部で単位を取ったときに仕入れたネタです。
ITEMAE
もともと、中国で、縦書きが「右から左」だったんですが、
その理由 ですね。 日本でも同じ理由です。  「かってに君」キーワードは、漢字2文字。 さあ、いってみよう。
ITEMAE
「書道ガールズ」では、左でしたね。
 左手で持ってたんですが。 左手で持ってたんですが。置いてあるバケツも左だった。 たらいを持って、特大筆の隣を走る子も。 
ITEMAE
おきまり・・・

ITEMAE
こういう続き方に感服

 正解!
正解!


アメリさんが見事ヒットしましたので、公開。
キーワードは「木簡」でした。 日本や中国で、古代の「書物」というのは、「木簡」でした。 (紙が発明されても、まだまだ貴重品で出回るのは後世) 木簡といいうのは、細長い板に文字を書き、 その後、上下を紐で繋いでいきます。 (書くときは、1枚板ですから、どっち向きでも、そう問題はありません。 手に持ったまま書くなら、左手に持って右手でサラサラ・・・) 読むときは、ズラーっと連なった板を引っ張り出しながらの作業になりますから、 力の入れられる「利き手」を使います。(右手で引っ張りやすいように、行は右から左。) よく、中国・始皇帝の思想弾圧事件、「焚書坑儒」について、 イラストで「焚き火に本を放り込んでいる」解説をする本があったりしますが、 当然、当時の儒教書は「木簡」ですから、じっさいは、書庫を丸ごと焼き討ちにしたはずです。 

↑5行もしたら「順番」がわからなくなるので、紐で繋いだんじゃないでしょうか。
 木簡といえども貴重品ですから、しょうもない文章を書くのには使わず、 公式文書とかお経とかの、重要文書。 (ころがして蹴っ飛ばしたりできる状況にはならない) ちなみに、奈良の遺跡で発見される「木簡」は、8割以上が「削りくず」だそうです。 (書いた文字は消せないので、削りながら使っていた。) これが古代史を知る上で役立ってます。 

新しく書いた木簡をつなぐのに、右手でつなぎやすい方向は逆なんじゃないかな〜、なんてモヤモヤしていました。読むときの便にあわせているんですね、なるほどナットク♪
|
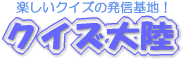

 解答判定ワード
解答判定ワード しちゃいますか?
しちゃいますか?  論理パズル
論理パズル 論理パズル
論理パズル 知識クイズ
知識クイズ