このクイズのヒント
-
ヒント知らないよ
このクイズの参加者(8人)
広告

広告
広告
広告
広告
クイズ大陸関連書籍


|

|
 ツイート
ツイート
|
 元の位置に戻れる? 元の位置に戻れる?
難易度:★★

既出かもしれないシリーズです。
第1問目 地球上のある地点Aから北に向かって真直ぐある距離行きB点に着いたとする。 B点からB点の東向かって東に向かって直ぐ同じ距離行きC点に着いたとする。 C点からも同様に南に向かって真直ぐに同じ距離行った時A点に戻ったという。 さてこの様なことは起こりうるのでしょうか? 第2問目 第1問目の 北-東-南 が 東-北-西 の場合は起こりうるのでしょうか? 第1問目とは違うA点でもかまいません。起こりえるのか起こりえないのか お考え下さい。 第3問目 太郎君と花子さんは全く別の位置にいました。太郎君も花子さんも 第1問目にあるのと同じように(北-東-南にそれぞれ真直ぐに同じ距離行く) 行動した時二人は最後に同じ地点に行き着きました。 さてこの様なことは起こりうるのでしょうか? 条件:地球は球状であるとしてください。(現実は違いますが計算が面倒なので) 全ての問題でなくても1問づつでもご回答下さい。 勝手に君は雇っていませんので内容により判断させて頂きます。 囁きについて 皆さんの囁きは基本的には公開させて頂きます。(公開時期は判断させて頂きます) 囁きの非公開を希望する方はその様に記載してください。 緑字 追記いたしました。申し訳ありませんでした 6/19 18:50
|


SHISHI1
うーん どう判断したら良いのでしょうか?
1行目の答えなんですが 2行目に書いてある理由で”北”に行けるのでしょうか? ものすごく無理みたいに思うのですが・・・ 2行目の答えなんですがその地点以外では如何なのでしょうか? 1、ある
最南端にいたとして、地球の1/4進めばありえる 2、ある 本初子午線、赤道が交っている点から地球を一周ずつ進むとありえる 3、ある 二人とも赤道上からはじめて、なおかつ、二人のうちどちらかが1/4進めば緯度の距離は1度ずれただけで距離が変わるのでありえる 

3は文字では説明しにくいのでいまいち伝わらなっかたかも
 ま、そこはおまけして 
SHISHI1
1、について
”最南端”とは南極点のことですか? 南極点から”北”へ行ったのでしょうか? 2、について 正解ですが”おしい” 3、について 北極点から” 確認なのですが、真っすぐというのは初めに方向を決めて、そっちにずっと進む(大円方式でしたっけ
 )と考えればよいのでしょうか? )と考えればよいのでしょうか?要は、途中で東西南北を確認したり方向転換をしたりしないのか、ということです。 第一問目(起こりうる) 例えば南極を出発地点として、赤道まで(地球一周の四分の一の距離)北に移動する。 (南極での「北」は全方向なので、この点に関して少し不安が残りますが…) 次に東進むのは赤道上の移動になるので、赤道上を四分の一だけ回る。 最後は南に四分の一周だけ進むと南極に戻る。 

SHISHI1さん、こんにちは
 その節はどうも…何か見たこととのある問題ですね  確認したいことがありましたので一問目だけです。 
SHISHI1
ボムボムさん こんにちは
 来て頂き有難うございます 来て頂き有難うございます  >確認なのですが、真っすぐというのは初めに方向を決めて、そっちにずっと進む(大円方式でしたっけ  )と考えればよいのでしょうか? )と考えればよいのでしょうか?要は、途中で東西南北を確認したり方向転換をしたりしないのか、ということです。 →はい その通りです。 ()内の不安・・・そこが問題になります。その点がクリアになれば’正解’ なんですがどうやって決定するのですか?決定方法を書いていただければ・・・ (正直言って私は決定方法は無いのでは?と思っております。) ↑
>要は、途中で東西南北を確認したり方向転>換をしたりしないのか、ということです。 >→はい その通りです。 ということは、赤道上では、第1問目、第2問目ともにありうるということでしょうか?でも、途中から北へ進んでいたのが南え進んでしまいます。最初に決めた方向なのでそれでも構わないならです。 

 
SHISHI1
マキチャンさん こんにちわ。
 4行目 について。 そこからどれだけ移動すればいいのですか? >途中から北へ進んでいたのが南え進んでしまいます。最初に決めた方向なのでそれでも構わないならです →全然かまいません。  現実問題両極点付近では東(西)に真直ぐに少し進んだだけでほぼ南(北) に進む事になるのです。又、例えば両極点から1mの所から極点に向かって 真直ぐに1m以上進んだ場合は反対方向に進んだ事になりますが、では 1m以内しか進めないのかと言いますと当然進めますよね。 よって方向を決めた地点からその方向にただひたすら真直ぐに進むものとして (途中でどっち向きに進んでいるかは気にしない)考えてください。
SHISHI1
第1問目 及び第2問目 正解おめでとうございます。
但し >>4 に囁かれた場所からだけでしょうか? 
SHISHI1
1 について 南極点から出発ですか?
南極点は360°どちらを向いても”北”です。どうやって進む方向を 決めるのですか?一義的に決定する方法を囁いていただければ 無条件に”大正解”に致します。 2 について それでは戻れないような・・・ 移動距離を地球一周にする。
A,B,C地点が異ならなければならないとは書かれていないので… 

前のコメントに対する答えではないですが、第一問のボケのような解答です
 ダメかなぁ?
SHISHI1
第1問目 正解です。 ただし・・・
この「ただし・・・」の意味は判りますよね 
まず、点Aが南極や北極以外であるとする。
また点A,B,Cは異なるとする。 このとき、点Aから北に、最後に南下して点Aに到達することを考えると極以外の点に南下北上で大円式移動で到達するには、初めと終わりの移動は同じ大円上を移動しなければならない。 したがって点Bも点Cもこの大円上の点であるはず。 これを大円1とする。 大円1上の点Bと点Cを、問題の意図から点Bでの東方向に進んだときの大円2で結ばなければならない。 点Bも極でなければ、東西南北が一義的に決まるので、この東西方向の大円2を考えたとき、これと大円1との交点のうち点Bと異なる交点は必ず点Bから見て地球の裏側になる。 したがって移動距離は地球の半周に決まる。 ところがこのとき点Aは点Bから見て南に地球の半周進んだところにあり、これはすなわち点Cのことになり、点A→点B→点C(=A)で最後に南に半周進むと点Bに戻る。 したがってこれは矛盾する。 上の議論は仮定 「点Aが極ではない」 「点A,B,Cがすべて異なる」 「点Bも極ではない」 の下での議論である。 まず、極において「東西南北」という方向を決定できないのであれば一番目と三番目の仮定は必要。 したがって点A,B,Cがすべて異なるのであれば、第一問はあり得ない。 以上からこの問題を考える上で重要なのは「極における東西南北」「点A,B,Cはすべて異なるか」ということに帰着される。 二つ目の「点A,B,Cはすべて異なるか」ということに関してはSHISHI1さんの意向次第なので保留します。 一つ目の「極における東西南北」については、南極においては全方向北であるので特定の「北」と言うにはなんらかの言葉を付け足さない限り、方向を指定するのは不可能と思います。 例えば「東経135度の北」とか。 ただ、特定の方向が分からなくても「結果的」にはどっちに進んでも北に進んでいるんですよね… まとめると、第一問は不可能、ただ「結果的に可能な場合もある」という条件付きで  

第一問をもう少し詳しく考えてみました。
難しいです…北はどっちだろう 
SHISHI1
下から 7行目>二つ目の・・・・に関して
についてですがそのような設定は一切しておりません。よって>>7の囁きを ”正解”にしております。そのような条件をつけた場合には>>3の囁きの 方法のみが正解になりえると思います。但しそれこそ 「北はどっちだろう」の疑問に答えなければいけないのですが 


一部の囁きを公開いたします。
この問題は元々 有名な問題である(このサイトにもあります) 「北に○km、東に○km、南に○km行った時元の位置に戻りました。さてここは何処」 の答えの1つである南極点に何かしら違和感を感じていたのですが、 rockyさん の「中学校理科のクイズ」(http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=6753) で「東に行く」の意味について考察していた時にその違和感が何処から来ているのか はっきりと判ったのでした。 つまり”南極点から北に行けるのか?”です。 皆さん御存知のように南極点は全方位”北”です。”東”、”南”、”西”は無いので 行けれないだろう事は直ぐ思いつくのですが果して北は? 「ある地点からある方向に行く」と言った行動をするにはその地点でその方向を一義的に 決めなければ行けれないのではないでしょうか? 例えば4人の人が南極点にいてそれぞれ 北、東、南、西に行くと決めたとします。 ここで北に行く人がある方向に行けばそれの90°右を”東”と決めて出発できるのか? 同様に”南”、”西”にも行けるのか? 非常に難しい問題だと思います。 皆さんの御意見をお伺いしたいと思います。  尚、現実の話として南極点には”アムンゼンスコット基地”があります。そこでも 無論気象観測をしていまして・・・そうです。何処から吹こうが全て北風になるのです そのため便宜上経度0を北として風向観測をしているそうです。 第三問目(ありえる)
移動距離を地球の外周の四分の一とします。 スタート地点はどこでもいいですが、極以外で太郎君と花子さんは別々の地点だとします。 まず北に四分の一だけ移動する。 移動後も極にはいないとします。 次に東に四分の一だけ回ります。 そうすると、四分の一周だと大円式移動では極以外では必ず赤道上に到着します。 で、ここから南に四分の一周すると、最後は二人とも南極に到達します。 最終的に同じ地点に到達するのではなく、一回目の移動で同じ地点に到達するのも許されるのであれば、例えば北極点を挟んで反対側にいるような状況も考えられる。 

二問目よりも三問目の方が先に分かったので先に囁きますね
 No.9について。 極はやはり特異点なので方位を決めるなんらかの方法が必要ではあると思います。 風向きをそのように決定しているのは知りませんでした 
SHISHI1
第3問目 正解 おめでとうございます。
5行目は3行目に一言加えれば問題ないはずです。 第2問目は 第1問目が判れば・・・ 最後の2行はそれでは余りにも・・・の問題ですので・・・ 1は南極点からなら可能です。
BからCへの移動は、あくまでA点を起点にした同一距離上の円周上の移動と言うことになり、どれだけ進もうが北に進んだ分だけ南に進むのだから同一点に戻ることになる。 2は北に行くだけになるため不可能。もしも360度進むことが可能であるなら赤道上であれば可能。 3は逆算すれば不可能なことがわかる。 同じ点から出発することになり条件に合わない。 

普通に答えたけど、なんかひねってあるのかなー?

SHISHI1
1 南極点から”北”をどうやって決めるのか?その方法を囁いて頂ければ
「大正解」とさせて頂きます。 (>>9を参照下さい) 2 後半の部分の所で移動距離等説明をお願いいたします。 3 えー そうなんですか? 「ひねっている」と言えるほどひねってはいません。あることを知っているか あるいは良く考えていただければ判ると思います。 ある地点から北または南にまっすぐ進むという場合、経線に沿って移動、
ある地点から東または西にまっすぐ進むという場合、 その地点を通る経線に直行する大円上を移動する、 という定義で考えました。 第1問目 起こりうる。 南極点、北極点を除く任意の点から出発し、 大円を一周して元の地点に戻る移動を3回すればよい。 第2問目 起こりうる。第1問と同様。 第3問目 起こりうる。 南極点をOとする。 北極点、赤道上の点を除く北半球上の任意の点をBとする。 Bにおいて経線と直行する大円と、 Oにおいて経線OBと直行する大円の交点のうち、東の方をCとする。 このとき、Bから東にまっすぐ進むとCに着き、 Cから南にまっすぐ同じ距離を進むとOに着く。 (大円の1/4を進むことになります) よってBからまっすぐ南に同じ距離を進んだ地点をAとすれば、 Aから北-東-南へまっすぐ同じ距離進んでOに着くことになる。 Aは南極点、北極点ではないので、 Oからの距離が等しい点A'を別にとれば、A'から同様の移動でOに着く。 

東にまっすぐ進む、とかの言葉の定義がよく分からなかったので静観していましたが、
はっきりしてきたようですので参加します  「南極点から北へいけるのか?」について 「南極点は360°どちらを向いても”北”です」 とありますので、どちらへ進んでも北に行ったことになると思います。 方向が一意に決まらない、ある地点のある方位がない、 というのは定義が不完全なだけだと思います。 それとも、どの地点においても全方位の存在と一意性をもたせるには どのように定義すればよいかという問題なのでしょうか。 この定義の問題には触れない回答を囁いておきます。
SHISHI1
最初の4行 正にそのような意図で問題を作成しております。
第1問目、第2問目 用意した答えと全く同一です。 正解 第3問目 出発点の条件が多少違いますが正解です。 全問正解おめでとうございます。 第二問も地球一周の距離を考えれば極以外からならば可能ですね。
ただ、それ以外にも可能な移動距離があるかどうかが気になるのですが、それが僕にとっては簡単には分からない問題で… もう少し考えてみます。 

あれが認められるならこれも…
SHISHI1
1行目 正解です。用意した答えと同じです。
2行目以降 その通りで私も色々考えたのですが、今の所は条件に合う ところが見つかっておりません。是非とも見つけて教えて下さい。  全問正解 おめでとうございます。 球面上での三角形で三辺の長さが等しいとき、平面と同じく正三角形となり、三つの角度も等しくなる…と思うのですが、証明は分かりません。
おそらく球面三角法の余弦定理や正弦定理なんかをいじくればそうなるだろうと思います。 上の仮定を認めたとして、三点A,B,Cが異なる場合に、三回の等しい移動距離のあと元に戻ってくるということは、三辺の長さが等しい正三角形を描くことになります。 東→北→西の移動において、北→西のなす角度は90度であるから、すべての角度は90度であるはず。 ところが最後の移動で西に移動して元の点Aに戻ったときに、そこからみて東とのなす角度は90度でないといけないので、これは北(or南)から元の地点に戻ったことになる。 また点Bでの東→北の方向転換でも同様に90度なすから、東への移動は赤道上でなければならない。 以上から移動の方法は、赤道上を東に移動し、点Bから北に移動、点Cから西に方向転換して元の地点に戻ったことになる。 移動距離は、点Cで西の方向転換してからもとの赤道上の点Aに戻ったということから、地球の外周の四分の一(or四分の三)であると考えられるが、その場合、点Cは北極点(or南極点)になり、極点では西を決められないということに反する。 以上より三点A,B,Cが異なる場合は極点で方位を決められなければ、題意を満たす場所はない。 

第2問を「あれじゃないときは…」と深く考えてみました。
SHISHI1さんが無いとおっしゃるならきっと存在しないのでは?  
SHISHI1
同様の論理で色々考えていたのですが、6行目及び7行目の仮定が正しい場合には
この論法は正しく、最後の2行に行き着くことになると思います。 ただ当然正しいと思われるこの仮定についてこのようにして使って良いのか 否か一寸自信が無かったので?としていました。 そして一番の問題に突き当たる事になるのです。 ”有っても決められないのでは?””無くてもこじつければ” この2点に対してスッキリとした答えが無い事には正解は出せそうに無いのです 
1は南極点からなら可能です。
BからCへの移動は、あくまでA点を起点にした同一距離上の円周上の移動と言うことになり、どれだけ進もうが北に進んだ分だけ南に進むのだから同一点に戻ることになる。 加えて、『北』はどの方角であろうとも、緯線に平行であれば良いわけで、最初の第1歩を踏み出した方向に歩みさえすればOK。東西は経線に平行な線であり、球状のものに対して90度左や右に行くものではないと思う。 2は北に行くだけになるため不可能。もしも360度進むことが可能であるなら赤道上であれば可能。 この問題の360度と言うニュアンスは、あくまで全てA点に戻ってくるわけですので、A点に対して進行方角へ360度分移動する(つまり地球を一周する)ことで、進行中の方角は無視しています。 北へ進む→南へ進む→北へ進む・・・で、赤道直下まで。って方向ですかね。 

付け足してみました・・・

SHISHI1
>南極点から・・(中略)・・最初の第1歩を踏み出した方向に歩みさえすればOK。
うーんその第一歩をどの様にしてどの方向に踏み出すか?が問題になるのです。 この問題の特性上(大円上移動)最初に方向を決めれば後は移動距離の問題 だけに集約されます。ただその最初に方向を決める方法が?なので。 2についてはもしも以下が多少違いますが移動距離は合っていますので正解。 

一通り正解を頂けたので、議題の核心であるNo.9のコメントについて考えてみます…
確かに東や西として方位を定義するのは困難かもしれませんが、現実的には極でも方向は存在するわけで… 「南極では全方向北」と考えているのであれば、我々が日本で使っている「東西南北」という言葉を極においても当てはめて考えるのがまずおかしいのかもしれませんね  もし原住民がいたとすれば、何らかの方位決定方法とそれに対応する言葉が存在してるのでは…と想像してしまいます  例えば天体を利用した方位決定方法とか? あるかどうかはわかりませんが… 

さて 1問目に付いてですが >>3の ボムボムさんの答えが成り立つ(南極から
出発できる)といたしますと、2問目もこじつけが出来るのでは? 赤道上から出発して東に1/4周移動、そこから北に1/4周移動(北極点)、 そこで後ろを振り向くと南なので左方向に1/4周移動 (ここでは”北を向いた時後ろが南で左が西”を使用しています) これで元の位置に戻って来られます。 これは1問目の南極から北に出発できるとしたら北に向かって後ろは南・・・と言った 理屈でどの方向にも進める事になると言った屁理屈を使っていますが、北には進めるが 他の方向には進めないと言った御意見をお持ちの方は撃破して見てください。 私個人的には 両極点は地理上の特異点であるため東西南北と言った概念を持ち込む ことは出来ない。よって極点では東西南北で表された方向に進む事は出来ない。 (数学で0での割り算は出来ないと同じような考え方) と思っています。 ↑現実的には原住民はいませんので判りませんがもしやるとすればやはり基準として 経度0度方向とかいった具合になるのでしょうか?しかしこの表記も極点にがぎった もので一寸外れると使用できませんし・・・ >現実的には極でも方向は存在するわけで… そうですね 前後左右上下と言った表現ならどんな時にどんな場所でも成立しますね ただ相対的な方向ですから位置の特定には使えませんが・・・ 

現状の定義を生かしたまま、南極点における北の定義だけ変更して
方位が一意的に決まるようにしようとしても無理があると思います。 任意の地点において方位が一意的に決まっている場合、 ある地点からある方位に進んだ後、逆の方位に同じ距離を進んだら 必ず元の地点に戻ってこないとおかしいと思いますが、 現在の定義では異なる地点から同じ方位に同じ距離を進んで 同じ地点(南極点など)に到達することができますので。 球面を3次元空間の一部として認識すれば、 前後左右上下で完全な方位を定義することはできますが、 球面上だけで完全な方位を定義することは不可能だと思います。 完全な方位としては一意性の他に連続性が少なくとも必要だと思いますが、 このような方位が球面上の全地点において定義できたと仮定します。 球面上の任意の点からある特定の方位にまっすぐある距離だけ進んだ地点を考えます。 進む距離を短くとれば、元の地点と移動後の地点は必ず異なる地点になるはずです。 この移動により球面が球面に移りますが、 球面から球面への連続写像は必ず不動点をもつという定理がありますので、 このような方位はありえない、ということになります。 球面ではなく、トーラス(ドーナツ状)だったら可能です  

いはらさんの
>球面から球面への連続写像は必ず不動点を持つ というのは、球面から球面の写像(x,y,z)→(-x,-y,-z)だと不動点は無いと思いますが… 込み入った数学の話は僕には手に余る部分が多いので、あまり深く議論できませんので…申し訳ないです…  そもそも日本での東西南北の決定方法はどのようなものなのでしょうか…? 方位磁石?太陽などの天体現象?それとも自転の方向から? 「皇帝様の建物の正面方向が南!」なんて方法では絶対ないですよね  (もし南極で文明が発達して、このような絶対的独裁的な決定方法が罷り通っていたとしたら方位は決まりますね(笑)) それはさておき、上のような決定方法を極に持ち込めるかどうか? この辺も重要だと思うのですがいかがでしょうか? 僕もSHISHI1 さんと同様、日本での決定方法は持ち込めず、したがって日本で考える東西南北という概念も成立しないと思います。 したがって現状は、新たに極での方位決定方法を考えないとどちらに進むかも決められない状態にあると思います。 現実的にはやはり天体現象から決めるのでしょうかね?  

>ボムボムさん
あれ〜?本当ですね  どこかでこの記述を見かけたのですが、だまされていたようです。 何か条件が抜けているのでしょうか??? 私も全く詳しくはないのですが、 不動点定理により、地球上には必ず無風地帯が存在する、 というのは有名な話ですよね。 この話も間違っているのか、別の形で不動点定理を使うのか・・・ ネットで検索してもよく分からなかったので、今度文献を探してみたいと思います。 東西南北の厳密な定義はどこかでされているんでしょうか。 恐らく南極点における方位について明確な決まりはないのではないかと思います。 南極点からはどっちに向かっても北で、南、西、東には進むことはできない、 というのが多数派だとは思います。 

いはらさん
ボムボムさん 色々検討していただき有難うございます。  >そもそも日本での東西南北の決定方法はどのようなものなのでしょうか…? この点に付いて (財)日本地図センターの地図のQ&Aの中で Q25.「北」とは、何を示す? A.地球は地球自身が回転しながら太陽の周りを廻っているのはご存知だと思います。地球が回転している軸は地球の重心を通り地球表面と交差する北側の点を北極といい、南側の点を南極といいます。地球上で北の方向とは、この北極点の方向のことです。北極星は、地軸の北の方向に極めて近い(1度くらいずれている)ところにありますので、夜、北極星を見つけて、その方向を北であると知ることができます。 (http://www.jmc.or.jp/faq/map5.html) となっています。つまり北は北極点とその地点を通る大円上で北極点に近い大円の方向 といえると思います。(自転軸はやはり天測でしょうか) >恐らく南極点における方位について明確な決まりはないのではないかと思います。 確かにその通りと思います。そのような決まりがありましたら>>9に書きましたように 風向を観測するのに仮に北を決める必要は無いでしょうね。 >不動点定理 申し訳ありません難しくて詳しくは判りません。(この問題との関連性も?) ただ(x,y,z)→(-x,-y,-z)の時(0,0,0)は不動のような・・・ >ある地点からある方位に進んだ後、逆の方位に同じ距離を進んだら >必ず元の地点に戻ってこないとおかしいと思いますが、 >現在の定義では異なる地点から同じ方位に同じ距離を進んで >同じ地点(南極点など)に到達することができますので。 私の単純なイメージは 通常の掛け算の場合、任意の数字Xにある数Yを掛けて 導き出された答えZにて結果のZと行程のYから元の数Xを求める事は可能ですが (極点以外なら方向が限定されますので戻る事が出来る)Y=0を掛けた場合 その答えは0になる(極点に到達する)ものの、逆の0で割る事でXを求める事は 出来ない(極点からは戻れない)といったものです。 このイメージで>>17に書かせて頂きました。 

>いはらさん
球面のコンパクト性(?)に関連がありそうですがよくわかりません。 どうも球面から球面で不動点を考える場合は写像の種類に依るようです。 写像度なる考え方があるようですが僕にはチンプンカンプン…  「写像度」「球面」「不動点」あたりで検索してみてください。 >SHISHI1さん (x,y,z)→(-x,-y,-z)は今は球面から球面の写像を考えますので、(0,0,0)は球面の要素ではありませんから… 球体であれば(0,0,0)は確かに不動点です。 ゼロのかけ算はうまい例えですね! なんとなく納得です  南極での方位についてですが、どうやら便宜的な決め方で済ましているように思えます。 ネットで「"東"南極大陸」や「"西"南極大陸」が検索に引っかかってきました。 これは「グリニッジを北に見た地図をよく使うらしく、そこから左右で東西を決める」というような記述でした。 現実では地理的な極と方位磁石から決める磁極に違いがあることが救いでしょうか。 全く同じ地点だと、南極で方位を決める道具がなさそうです。 天体を使っても自転しているせいで、ある時刻で特定の方向をさすものがあっても、時間が経つと違う方向をさしているような気がします。 

論点がずれていたようで、申し訳ありません。
確かにこの問題には直接関係はないのですが、現在の定義では、 南極点、北極点の方位をどう考えてもおかしいところがでてくると思いましたので、 全地点での方位の定義を考え直して、 任意の地点の方位が一意的に決まるようにできないのかを考察してみました。 不動点定理によりそのような方位は定義できないことが証明されるのでは、 と思った次第です。 で、考え直してみたのですが、 地球上で無風地点が必ずあるという話が正しいものとします。 任意の地点で方位が一意的、連続的に定義できると仮定すると、 全地点で例えば北風が吹いている状態を考えることができますが、 これは無風地点が必ずあるということに反するので、 そのような方位は定義できない、ということになると思います。 現在の論点は、南極点で特定の方向、例えば日本の明石市 に向かいたいという場合、実際にその方向を知るにはどうすればよいか、 ということでしょうか? これは、自分の現在位置が分からない場合に、 その地点の緯度、経度を求めることと本質的に同じ問題だと思います。 南極点から任意の方向に一歩踏み出し、その地点の緯度、経度が分かれば、 それを基準にして南極点からの方向を決めることができるはずです。 緯度、経度を求める方法ですが、 GPSだと、人工衛星からの信号を基に計算しているようです。 人工衛星を使わない場合、 緯度については北極星の観測で分かると思います。 経度については天体の観測だけでは分からず、時計が必要なようです。 時計があれば計算できるということのようです。 航海時に現在位置(経度)を知るために、正確な時計が必要だということになり、 揺れる船の上でも正確に時を刻むクロノメーターが開発された、 という歴史があるそうです。 

>いはらさん
確かに今議論していることがあやふやになってきましたね  僕は 「極での東西南北とは?」 「実際に極で特定の方向を見いだす方法は?」 の両方が議論なのかなと思い、その両方について言及してきました。 ただ、問題の書き方なんかを考えると後者は不必要だった気がします… なのにダラダラと書いてしまって申し訳ないです  議論の焦点は主であるSHISHI1さんに今一度確認したいのですが  いかがでしょうか? いかがでしょうか?

>いはらさん 色々詳細な検討、有難うございます。
>地球上で無風地点が必ずあるという話が正しいものとします。 >任意の地点で方位が一意的、連続的に定義できると仮定すると、 >全地点で例えば北風が吹いている状態を考えることができますが、 >これは無風地点が必ずあるということに反するので、 >そのような方位は定義できない、ということになると思います。 これって仮定が一つでは無いような?全ての仮定が真の時のみ真になりますので (それとも無風説は真なのですか?直進と回転のみですから真のような気がするのですが、 又、全て北風状態の仮定に無理は無いのか?通常考えて無理は無いと思いますが) この結論に直結しても良いのでしょうか? >現在の論点は、南極点で特定の方向、例えば日本の明石市 >に向かいたいという場合、実際にその方向を知るにはどうすればよいか、 >ということでしょうか? この問題の論点とは一寸違うと思います。(但し議論していただくことは問題ありません) この問題では言葉、概念その他どのような定義をしていただいてもかまいませんが 南極点から”北”(東、西、南)に行けるのか?です。 現在私はこの事につき二つの仮定をしたみたいです。(今気が付きました  ) )・”行く”にはその方向を一義的に決めなければならない。 これはA地点からB地点に行くには方向と距離の決定が必要だと考えているからです ベクトルとスカラーになるのでしょうか?この問題では距離は任意ですので ベクトルの決定が必要では無いかの問題になるのでしょうか? ・南極点にて東西南北にて表記した方式で方向を一義的に決めれるのか? 当然南極点では360度”北”ですから・・・ >緯度については北極星の観測で分かると思います。 >経度については天体の観測だけでは分からず、時計が必要なようです。 >時計があれば計算できるということのようです。 そうですね緯度は天測(現実的には南中時の高度のからの計算になるのでしょうか)と 経度は南中時の時差(基準時からの誤差から15度/時間で計算)になるのでしょうか? いずれにしても南中(北半球では、南半球では北中?)の観測なのでしょうか? >ボムボムさん お手を煩わせ申し訳ありません。 >(x,y,z)→(-x,-y,-z)は今は球面から球面の写像を考えますので、 >(0,0,0)は球面の要素ではありませんから… 確かにその通りですね。  でもあえて言い分けさせていただきます。 でもあえて言い分けさせていただきます。単純な私は”球面”は3次元的に閉じた2次元と思っていますので、 2次元的に考えると種々の”インチキ”が出来うるとも思っています。 表された方法が平面座標系の3次元でしたので無意識のうちに3次元と思い込んで いました。  やはり球面を論ずるなら極座標系で半径方向のrを除いた(θ,ω)系 やはり球面を論ずるなら極座標系で半径方向のrを除いた(θ,ω)系の方が判りやすく(2次元ですから)つまり (θ,ω)→(θ+180,-ω) になるのでしょうか?考えて見ます。 >「極での東西南北とは?」 >「実際に極で特定の方向を見いだす方法は?」 >の両方が議論なのかなと思い、その両方について言及してきました。 こう言った問題の場合当然波及的に他の問題が発生すると思います。 その発生した問題が主問題を解くにあたって必要か否かはありますが問題に対して 検討することは無意味ではないと思っています。(是非やってください) ただ複数の問題に対して検討する場合当然主題の違いにより検討内容に違いが出るので しょうが、誤解を生みかねないとも限りません。 ここからはお願いになるのですが、検討される主題に付き明記していただけますと このような誤解も生まれにくくなると思います。 後、判り易い簡単な例がありましたらご紹介ください。 (不動点定理で縮小コピーを重ね合わせる例えは判りやすかった) 

>SHISHI1さん
派生した議論への寛容な対応、ありがとうございます  では、改めていくつか思うところを述べさせていただきます。 不動点定理のわかりやすい反例というか… 例えば一次元球、すなわち二次元で原点からの距離が等しい円周を考えます。 このとき原点周りの回転操作によって再び自分自身に戻ってきます。 (θ)→(θ+δθ)と書けばいいでしょうか。 この場合δθは2πの整数倍でない限りは不動点を持ちません。 一方でネットでは、数直線を考えた場合の一次元での不動点定理の例えに 「ゴムのひもを引っ張ると動かないところがある」 ようなものが挙げられていました。 このように、どうも不動点定理が成り立つ場合と成り立たない場合があるのは確かなようで、定理を適用するために満たすべき仮定があるためだと思います。 三次元でも同じように、満たすべき仮定を満たしていないと、このようなことが起こると思います。 (x,y,z)→(-x,-y,-z)という変換が、実際の球面をどのように変形させているのか、上の円周の回転のように表現することが難しいですが、例えば球面座標を導入して(θ,φ)を用いて(x,y,z)=(sinθcosφ,sinθsinφ,cosθ)とすると、(x,y,z)→(-x,-y,-z)の変換は(θ,φ)→(π-θ,φ+π)とすればいいと思います。 僕が思うに… 一次元球を数直線上の区間と等価なものとみなすことは確かにできますが、上の回転操作を、等価と見なした数直線の区間[0,2π)に当てはめるたときに、2πのところから0に戻るためだと思います。 不動点定理を使うときに、写像が連続性を満たしていないとダメなのですが、ここに関わってくるかと… 不動点定理はとりあえずこのくらいで… 「極での東西南北について」 やはり持ち込めないと思います。 これは無風地帯が正しいとすればその説明から転用できるかと思うのですがどうすればいいのかちょっと思いつきません  「南極での特定の方向に進む方法」 いはらさんの方法で確かに自分の居場所はわかりますが、自分の居場所がわかっても方位はわからないのでは? 少なくとも方位を決めるには、ベクトルとスカラーという意味を考えると二カ所ではかる必要があると思います。 僕が思うのは 「確かに極で東西南北は決められないが、例えば、極圏で通用するような新たな方位決定方法(と、ついでに新名称も募集)は無いのかな」 という疑問です。 この方位は、現存の"東西南北"とは違っても構いません。 この新たな方位決定方法が見つかれば、その方位決定方法における極(特異点)は存在するであろうが、それが遥かに離れていれば問題ないだろうと。 そういう意味を込めて 「実際に極で特定の方向を見いだす方法は?」 を考えていました。 これさえできないのであれば、緯度経度を使ったホントに便宜的なものしか使えないと思います。 例えばいはらさんの現在位置を知る方法では、これから行く先がわかっていないとできない方法ですよね。 それに対して「北に10km」というのはこれから行く先がどんな地点か知らないが、でも方位磁石などを使ってスタート地点から北に10km進むことはできますよね。 なんて言ったらいいのか、言葉が出てこないのですが… 「今いる場所だけで、なにかしらの現象を使って普遍的な方向を決めることはできるのか」と言えばいいんでしょうか。 今現在自転軸と地球を大きな棒磁石と考えた場合の磁極が近いので、極圏でなければ方位磁石を使うことでほとんど問題なく方位を知ることができます。 ところが、例えば今の地球の棒磁石が90度傾いていた場合はどうでしょうか? この場合は、自転の極と磁気的な極が一致しないので、自転を基準にした北極の方向を知るには天体現象を使う必要があると思います。 一方で、自転基準での極圏の人たちにとっては、生活する上では棒磁石を使って方位を決めることができ、例えば「磁北」に10kmというような移動方法が採れると思います。 でも磁極と自転の極が一致しているときは、磁石を使っても方位を決めることはできなくて、代わりとなる方位決定方法はあるのかな…という疑問です。 長々と書いてしまいましたことをお詫びします。 

 「不動点について」 「不動点について」位相幾何学の本を読んで勉強して参りました。 その本によると、不動点定理の集合については、 コンパクト(有界閉集合)かつ凸という条件が必要なようです。 円周や球面はコンパクトではありますが、凸ではないため、その条件を満たしていないようです。 円板(円周及びその内部)、球体(球面及びその内部)は、コンパクトかつ凸なので、 円板から円板、球体から球体への連続写像は必ず不動点を持ちます。 地球上に無風地帯が存在するという話は正しいのですが、 不動点定理ではなく、 球面上の連続なベクトル場は必ず特異点を持つということで示していました。 書いてあった証明には納得しましたが、長くなるのでここには書きません。 というわけで、無風地点の存在をもとにした議論については正しく、 全地点で一意的かつ連続な方位は定義することができないということになると思います。  「南極点から”北”(東、西、南)に行けるのか?」 「南極点から”北”(東、西、南)に行けるのか?」東、西、南は定義されていないので行くことはできないと思います。 どの方向に進んでも北に進んだことになると思います。 恐らくSHISHI1さんが気にしているのは、 通常ある地点から北にある距離進んだといった場合に、その経路が完全に特定できるのに対して、 南極点から北にある距離進んだと言った場合は、経路が特定できないのがおかしい。 北は北でもどの北なのかはっきりしてくれ〜ということではないかと思います。 これは現状の定義でははっきりさせることはできません、というしかないですね。 方向をはっきりと示したい場合は、経度を使えばよいと思います。  「南極での特定の方向に進む方法」 「南極での特定の方向に進む方法」>いはらさんの方法で確かに自分の居場所はわかりますが、自分の居場所がわかっても方位はわからないのでは? >少なくとも方位を決めるには、ベクトルとスカラーという意味を考えると二カ所ではかる必要があると思います。 南極点から一歩離れた地点の位置を測定するわけですから、 南極点を含め2点の位置が分かったことになります。 その2点を結ぶ線(測地線=大円の一部)を基準にすれば方位が決められると思います。  「実際に極で特定の方向を見いだす方法は?」 「実際に極で特定の方向を見いだす方法は?」極だけの話でいいのなら、地面に経度0の線を引いておけば、 それを基準に方位を決められると思います。 

いはらさんの書き方に倣って…
 「不動点について」 「不動点について」無風地帯は不動点というより特異点だったんですね。 これでとりあえず、方位が決められない点があることはよさそうですね。  「南極での特定の方向に進む方法」 「南極での特定の方向に進む方法」確かに南極と一歩進んだ先で観測しているので、二点測定したことになりますね。 失礼しました。  「実際に極で特定の方向を見いだす方法は?」 「実際に極で特定の方向を見いだす方法は?」>極だけの話でいいのなら、地面に経度0の線を引いておけば、 >それを基準に方位を決められると思います。 そうなんですが、それはやはり便宜的な決定方法だと感じるのですが… 方位磁石や天体の回転のように自然現象(?)を使った方法はないのでしょうか? 

 「不動点について」 「不動点について」御説明有難うございます。 イメージ的にはベクトル場からの「無風地帯が存在する」も含め判るような気がします。  「南極点から”北”(東、西、南)に行けるのか?」 「南極点から”北”(東、西、南)に行けるのか?」行けれるが決めれないと言った状況なのでしょうね。何かパラドクス的な面があるのでは? 行けれるが決めれない→決めれないのにどうやって行くのか? やはり疑問が残ります。   「実際に極で特定の方向を見いだす方法は?」 「実際に極で特定の方向を見いだす方法は?」確かに極では経線方向で示せれるのですが、あくまでも極に限定した表現になるのでは? 「東西南北」が極で使えない逆で極でしか使えない方法と思います。 何処ででも使える普遍的な表現は無いのでしょうか? ************************************** 問題の主回答から一寸外れた議論は置いて、では用意した答えを書いておきます。 前提条件 移動は大円上を移動する から 大円上移動の特徴は ・大円同士は必ず交差する(赤道、経線は大円ですから確認して見てください) ・大円の交差でそれぞれ2等分する(同上) ・極、赤道上以外の点から経線に直角に引かれた大円は±1/4周の点で赤道と交差する 等があります。これらの点を踏まえると 第1問目 北−東−南 の移動ですから北と南の移動は同一経線上(±180線を含む、以下同じ) の移動ですから東に移動する前と後で同一経線上でなくてはいけません。 東への移動で同一経線上になるのは1/2*n周(n=自然数)になるのですがn=1のとき、 3回の移動が同一距離のため 2回目には出発点に戻りますが3回目には180°反対の 点となり条件を満足致しません。よってn=偶数となり移動距離はN周(N=自然数) が正解となります。 但し両極から北に進めないと仮定すると「両極を除く」が条件になります。 南極点から出発できる条件では 南極点からM+1/4周も答えになります。 又、北極点から出発できる条件ですと 北極点からM+3/4周も条件を満足します。 2問目 1問目と同様な考え方で 両極を除いてN周が答えです。 両極から西(特定の方向ですが)に行けれるとすると 赤道からM+(1/4or3/4)周も 条件を満たしております。 3問目 東に1/4周移動すると必ず赤道上に来ますので 両極及び赤道上以外からM+(1/4or3/4)周で1/4の場合は南極点、3/4の場合は北極点 で出会えます。 さてここで上で N と M を書き分けたのですがこれは N:1,2,3・・・ M:0,1,2,3・・・ をイメージしていた為です。 この問題では移動距離を任意にしていますので 1,2問目で移動距離が0(N=0)でも 条件は満たしております。これも正解にするか否かは?なのですが・・・ では、今までの皆様の囁きを公開しておきます。 |
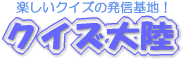

 頭の体操
頭の体操 頭の体操
頭の体操