���̃N�C�Y�̃q���g
-
�q���g�m��Ȃ���
���̃N�C�Y�̎Q���ҁi13�l�j
�L��

�L��
�L��
�L��
�L��
�N�C�Y�嗤�֘A����
|
|
�Q���^�i�]�g�L�T�C�g�w�N�C�Y�嗤�x�ŁA�]�g�����ǂ����I |
@quiz_tairiku������t�H���[ |


|

|
 �c�C�[�g
�c�C�[�g
|
 ���m�̔��� ���m�̔���
��Փx�F������ �@

���̓��e�ł��I��蕶���悭�ǂ߂Ε�����Ǝv���܂�
 �Q�O�O�V�N�Q���P�X���i���j�P�W���R�T���E�E�E �Ƃ��錤�����łP�l�̔��m������t�̂����܂����B ���̉t�̂́A�ǂ�ȕ��ł��n�����Ă��܂��t�̂������̂ł��B �����������m�͂��̂ǂ�ȕ��ł��n�����Ă��܂��t�̂��g���Ď��������܂����B ���m�͂ǂ�ȕ��ł��n�����t�̂̓������r���������Ă��āA�����p�̂˂��݂ɂ����܂����B����ƁA�˂��݂݂͂�݂邤���ɗn���Ă䂫�����͑听���I ���m�͌����A�唭���������̂������E�E�E�B ���āA���ł��B���̕��͂ɂ͂������ȓ_���P����܂��B ����͈�̂ǂ��ł��傤�H
|



�u�ǂ�ȕ��ł��n�����t�̂̓������r���v
�ǂ�ȕ��ł��n�����Ȃ�A���̉t�̂��������r�����n����͂��ł��B �������Ă܂����H 

�u�����܂�v�ł���
 �Ƃ���ŁA���m���F���X�e�[�V�����Ō������Ă����炱�̌���ł͂Ȃ��Ǝv���̂ł������������������l���ɂȂ�܂����H ���ł��n�����t�́��@�i(�@�� �j)�@�t���t�� 

����̋�C���n�����̂ł��ˁB�_����
 �Ȃ��A�t���t�����Ď��͂̕ǂɂ���������A������ρB  �́A�u�l�R�W�����s��11�l�v(���Ђ����� NHK)�Ƃ����ԑg�ŁA�u�A�J���x�����v�Ƃ�����i���o�Ă��܂����B �͂��߂́A���ł����ɕς��Ă��܂��Ƃ����ݒ肾�����̂ł����A�r���Łu�l�ԂƁ����Ɓ~�~��.......�ȊO�͐��ɕς��Ă��܂��v�Ƃ����ݒ�ɕς���Ă܂����B������Ǝv���o���܂����B  

��C���n�����āA���m�����`
 �������A�n�������Ă����̂͌ő́E�C�̂ɂ��Č����܂�����ˁB �t�̓��m�Ȃ�ǂ��Ȃ�ł��傤�H �G�^�m�[���͐��ɗn���饥��B����ς��߁H�B �t�̂ɂ��̂�n�����ƁA��ʓI�ɗn�����\�͂͌���܂���˂��H �̐ς̐��{�̌ő̂�n�����t�̂Ƃ��������C�����܂����A���E������͂��B �Ƃ������ƂŁA�ʉ�_���ŁB �u�t�̂̓r���̕ǂ�n�������B�������A�r���̐������n�����݂ƂƂ��ɁA�n�����͂���܂�A�˂��݂͂т���G��ɂȂ��������������v �������H�������炲�߂�Ȃ����B  ���o�c�i���� ���ׂĂ݂�ƁA���܂�邸���ƑO�̔ԑg�ł������܂��B�o�c�i������y�� �A�J���x������O�������ď��܂����A���Ȃ��͍̂���̐l�ނ̃e�[�}���������Ă��ꂻ���ȂƂ�  �܂��A�����ɂ͓���Ȃ��ł��炢��������ł��B 

�u�A�J���x�����v�́A�u�`�t�v�Ɓu�a�t�v���������u�ԂɁu�l�ԂƔL�ƃl�Y�~�v�i�o��M���ނ͂��ꂾ���B�J���X�̓A�E�g���������H�j�𐅂ɕς����ɂȂ�c�B
�@���Ȃ݂Ɂu�A�J�v�͐��̂��ƁB���e���ꂾ���������A�{�[�g���Łu�A�J�������v�Ƃ����ƐZ���̋��ݏo���̂��ƁB��������͂��̎�̘b�ɖڂ��Ȃ��c �i���ǁA�n���𐅐Z���ɂ���Ƃ�ł��Ȃ��v�悾�������A�Ƃ�ł��Ȃ������H���Œn�����~�����l�R�W�����s�̐l�X�c�߂ł����߂ł����j 

��000����
�u�ǂ�ȕ��ł��n�����̂Ȃ炻�̃r�����n����͂��ł��B�v �w�ǂ��܂ł��x�n�����A�Ƃ͏����ĂȂ������̂ŁE�E�E ��ITEMAE���� �u�`�t�v�Ɓu�a�t�v���Ă�����ƋÂ����ڒ��܂݂����ł��ˁB �w�F�w�F�w�F�w�F�w�F�B�w�F�ڂ��~����  �u�A�J�v�f�~�b�N�Ƃ����ł����B�m���͐�����i����j���܂��H�͒m���I�Ƃ����܂������ 

�̂Ԃ����Ɠ��l�ǂꂾ���n�����邩�����ėL��܂���ł����̂�
�ʉ�_���� �ǂ�Ȃ��̂ł��n�����t�̂͂˂��݂�n��������˂��݂����Ă����P�[�X�A �������̏���n�����čs���n�ʂ�n�����Ǝ���̊�Ȃǂ�n�����Ȃ���n���� ���S�Ɍ����i��ł������B�n���̒��S�ł͊j���n�������Ƃɂ��d�̓o�����X������ �n�\�ł͒n�k�Ȃǂ������A�����͑��₦��������ɏd�͂ɂ����N����Ō�ɂ� �n�����ׂėn���Ă��܂����B �ƂȂ�̂Łu�����A�唭���������̂������E�E�E�B�v�ł͖����n����j�ł������B  

���ꉻ�w�����H�����č�����u�ԓ��ꕨ�������Ⴂ�܂���
 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�˂��݂̂��炩���ߓ������r���ō��Ƃ����邩���@���Ď����Ă��Ă�����ł��߂����E�E �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�˂��݂̂��炩���ߓ������r���ō��Ƃ����邩���@���Ď����Ă��Ă�����ł��߂����E�E  

���X�l�[�N����
�ǂ��ł��B�Ӑ}�ƈႤ�Ƃ���Ő���オ���Ă��݂܂���  ��SHISHI���� �ǂ��܂ł��n�����������  

�ǂ�Ȃ��̂ł��n�����̂Ȃ�A�r�����n���Ă���͂��ł��B
����ɁA�ǂ�Ȃ��̂ł��n�����̂Ȃ�A��C���n���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �r�����n���Ȃ������Ȃ�A���̉t�̂͋�C�Ɖ��w�������N�����Ă��ׂĕʂ̕����ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �Ƃ���ƁA�l�Y�~���n����͂��������B�Ƃ����Ƃ���ł��傤���B 

���ł̃l�^�ŁB
�u�t�́v�ɖڂ�D���܂����A �u�K���X�͉t�̂��v�Ƃ����������炢���A�˂��݂ɐG�ꂽ�i�K�ŔS�����������i�ŁA���������r���̒��ł́A�K���X��c�B 

�K���X�́A����܂��s�v�c�ȏ�Ԃł���ˁB
����Ȃ܂ɂ������ȃl�^�A�ޗ��₳��ł���  �m���ɁA����Ȃ炤�܂��˂��݂����n�����܂��ˁ[ �āA�X���傳��A�������b�N���Ȃ��Ƃǂ�ǂ�}�j�}�j���Ă��܂��܂���[�B �N�C�Y����߂�����Ă�������  

>�X���傳��A�������b�N���Ȃ��Ƃǂ�ǂ�}�j�}�j���Ă��܂��܂���[�B
���͐V���i�u�ǂ�ȕ��v�Ƃ����l�[�~���O�̉n���v���X�`�b�N��n���������ŁA�K���X�r�܂ł͗n�����Ȃ�����  

���˂��݂݂͂�݂邤���ɗn���Ă䂫�����͑听���I
�˂��݂�n�����������Łu�听���I�v�Ƃ�����̂Ȃ�A �u�ǂ�ȕ��v�Ƃ̓l�Y�~�̐V�i�킾�������H    

�u�Ƃ肠�����r�[���v�Ƃ������������ƁA�������Ęb�Ɏ��Ă܂��ˁi�ǂ����I�j
�u�˂��݂�n�����Ă����ׂĂ̕���n�������Ƃ̏ؖ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��v �����Ɖ��_�ł����_�ł��n���Ȃ������ȁA��������ʂ�n�����Ȃ��ƁB �_�C�������h�Ƃ��A���m��覐Ƃ��A�@�ێ��Ƃ� ���₶�M���O�œ�����������̐S�Ƃ��E�E�E  �܁[���A���܂��[�悧�[�̂Ԃ���[�� 

���Ƃ��A���剻�������J�����鎞�́A�����ɏ������Ȃ����J�����Ȃ���
�����Ȃ� ���Ă̂́A�}�b�h�T�C�G���e�B�X�g��̏펯�ł��傤  ������A���ׂĂ̕���n�������̂ł���t�̂��J�����鎞�́A�����ɁA �����n���Ȃ��r�����J������ׂ��ł��B �i�����ɗn���Ȃ����n����̂Ɏ��Ԃ�������j ����Ȃ��̂́A�}�b�h�T�C�G���e�B�X�g��̏펯�ł��i�R 

���}�b�h�T�C�G���e�B�X�g��
kan����f���炵���I�}�b�h�T�C�G���e�B�X�g������]  

�������n���Ȃ��r�����J������ׂ��ł��B
�ǂ�ȏ��ł��т������c�݂����Șb�ɂȂ�܂��ˁB  

���̎��͈�肾���ǁA���͓˂��͂ɂ���Ĕj��͂��������疵�������݂����Șb������܂����A
���������������Ă��܂��Υ���Ƃ��肪�Ȃ����Ęb������܂��ˁB �n����X�s�[�h����_�H�������A�ł����� 

�ǂ�ȕ����n�����̂ł�����
�˂��݂�n�������߂ɁA�r�����A �����Ă��鎞�r�����n���Ă��� �̂ł͂Ȃ��ł��傤���@  ���̌�̂��Ƃ�z������ƃr�����n���� ���ɂ��ڂ�ď����E�E�E�@���[��  �n�����Ⴂ�܂��ˁB  

�u����v���u�听���v�ƌ����Ă����A
����ς�l�Y�~�̖��O���u�ǂ�ȕ��v  

�@�ǂ�Ȃ��̂ł��n���������Ȃ���A���̈ȊO�̂��̂ŕ������߂�����B
���Ƃ��A�d�́A���͂Ȃǂ��߂ł��傤���B �A���Ƃ��A�@���\�Ƃ��Ă��A�ǂ�ȕ��ł��n�����Ƃ������Ƃ́A���̗n�t���́A�����Ŏ�����n�����Ǝv���܂��B�n�����Ƃ������Ƃ́A���q���x���̉��w�����Ǝv���܂��B��������ƁA�����Ŏ�����n�����Ȃ���A�Ō�̂P���q�����c��Ƃ������Ƃł��傤���H 

�悸�h�n�����h�̒�`�͒u���Ă����܂��āE�E�E��Ԃ̖��ɂ���
�ł́A�}�b�h�T�C�G���e�B�X�g�ɂȂ�ׂ��A���������Ƃ������Ȑ����I������  ���ǂ�ȕ��ł��n�����t�̂̓������r�� ���̒�`������̂ł����A�����Ƃ��čl�����ꍇ�ɂ͂��̉t�̂ƐڐG����S�Ă� ������n�����\�͂�����t�̂ƍl�����܂��ˁB ���̂悤�ȉt�̂����Ă����ɂ́@>>2�ł̂Ԃ���ꂽ���d�ʋ�ԁA >>25�Ń}�L�`���������ꂽ�d�́A���͂Ȃǁ@�͐悸�l�����܂��B ��������C���ł���Ȃ瓖�R��C�������ł�����n�������ƂɂȂ�܂��ˁB �i>>3�@��PDJ���w�E����Ă���܂��B�j �Ƃ���ƕK�R�I�ɐ^�ɑ��̕����Ƃ͔�ڐG�ŕۊǂ��鎖�ɂȂ�܂��B ���̉t�̂���������̂��ۂ��͕s���ł����ʏ�̉t�̂Ɠ����悤�ɏ�������� ���肵�܂��Ɛ^�ł͂Ȃ��t�̂̏��C���ƂȂ�܂��B �����ʼnt�̂͂��̉t�̂̏��C��n�����āi�Ïk���āj�t�̂ƂȂ蓯���ɏ��� ���ď��C�ɂȂ�ƍl����A���C�ɗn�����\�͂�������A���炩�̗͂ł��̉t�̂� ���C�ȊO�Ɣ�ڐG�ɂ��邱�ƂŁh�r���h�ɓ����͉̂\�ɂȂ�܂��B ���������C���t�̕\�ʈȊO�̃r���̓��ʂŋÏk�����ꍇ�ɂ͓��R�r���͉����܂��̂� �r�����ʂŋÏk���Ȃ����������ɂȂ�܂��B �����ł�������i��ł��̉t�̂��Ō`�����������l�����ꍇ�A���̌ő̂��n�����\�� ���Ȃ��ꍇ�ɂ͌ő̕\�ʂʼn����ĉt�̂Ɂi�n���j�ł܂�ő̉��i�������H�j�� �������s�I�ɋN�����Ă���ƍl����Ƃǂ��ł��傤���H ���̉t�̂̌����y�я��C�ɂ͗n�����\�͂������̂ŁA���̌����ō���� �r���ɓ���A�ʼnt���t��Ԃɂĕۊǂ��� �ŁA�r���͗n������̂̕ۊǂ͂ł���͂��ł��I  �i>>19�@��kan��������Ƃ���}�b�h�T�C�G���e�B�X�g��̏펯�ł������  �j �j���āA�h�n�����h�ƌ��������t�̈Ӗ��A��`�ɂ��Ăł����E�E�E ���������Ă͂�����Ƃ͔���܂���B�ʏ풼���v�����̂� �@1.�ő̂��t�̉�����ꍇ�@��F�X��n�����Đ��ɂ��� �@2.�������n�}�ƂȂ葼�̕�����n���Ƃ��� �@�@�@��F�@�n�}-���A�n��-�����@�����𐅂ɗn���� ������܂��B���̉t�̂��ǂ���̈Ӗ��́h�n�����h�Ȃ̂��͕s���ł��B �O�҂��Ƃ���� �ڐG�����ő̂͑S�ĉt�̂֕ω����鎖�ɂȂ�܂��̂ŁA�n���͉t���ɂȂ�ł��傤�B  ��҂��Ƃ���Ɨn��\�͂Ɍ��E�����邩�ǂ������傫�Ȗ��ƂȂ�A �����ꍇ�ɂ́@�@�S�Ă̌ő̂�n��������̂Œn���͉t���ɂȂ�ł��傤�B  �L��ꍇ�ɂ́@�@�˂��݁A�E�E�E�E��n�����Ă���Ɨn�����\�͖͂����Ȃ����B  �ƂȂ�ł��傤�B >>25�@�̃}�L�����̇A�̐��ɂ��Ắh�n�����h�̈Ӗ����ǂ��l����̂��H �n�����ꂽ���̂͂ǂ��Ȃ�̂��H�i�n�����ꂽ���̂́h���h�ɂȂ�̂ł���� ����̂ł����E�E�E�j ����������2��ȊO�̗�A���͒�`������܂������̂�������Ƃ����z��ɂȂ� �Ǝv���̂ł����A�@���Ȃ��̂ł��傤���H 

�r�g�h�r�g�h�P ����@�킴�킴���J�ȉ�����肪�Ƃ��������܂����B
 ���[��B���������Ă݂�A�n�����Ƃ������Ƃɂ��āA���R�Ƃ����l���Ă��܂���ł����ˁB���̏ꍇ�A�n�����Ƃ����̂́A�̂��t������ƂƂ�̂����ʂ̂悤�ȋC�����܂��B���������āA���̉t�̂��A�����Ŏ�����n�����Ƃ����̂͏������������悤�ȋC�����܂��B �ƁA�����܂ŏ����ċC�������̂ł����A ����C���ł���Ȃ瓖�R��C�������ł�����n�������ƂɂȂ�܂��ˁB �Ƃ���悤�ɁA�n�����Ώۂ͌̂Ɍ��炸�A�����ł���ˁB ���̏ꍇ�A�n���������ʁA��C�͂Ȃ��Ȃ���̂Ǝv���܂��B ���������āA��͂�A�����Ŏ�����n�����A�n���������ʂ͂Ȃ��Ȃ�A�Ō�̂P���q�������c��̂��ȂƁA���ɖ߂����肵�Ă��܂��܂��B ��C������A���R�A���̉t�̂ɐڐG���Ă����C���������̂ł��傤����A���l�ɁA�����ƁA���̉t�̂ɋ߂��A�������g������������̂ł͂Ȃ����ƁA���ɂ͎v����̂ł����B  �n�����Ƃ����̂́A���̏ꍇ�A�Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃł��傤���B ���ɒ��J�ɉ�����Ă��������Ȃ���A���̂��炢���������ł��܂���B  ���萔���|�������\����܂���ł����B 

�Ăу}�b�h�T�C�G���e�B�X�g�ɂȂ�ׂ��A���������Ƃ������Ȑ����I������
 �ł͂����ł��́h�ǂ�ȕ��ł��n�����t�́h�̗n�����@�\�ɂ��Ẳ����v���܂��B ���̉t�̂͂��̉t�̈ȊO�̕����ƐڐG���܂��ƐڐG�_�ɂđ���̕����� �f���q���x���ɕ������A�����i�ǂ�ȕ��ł��n�����t�́j�Ɠ���\���ɍč\�z���� �ƌ����������������Ă��܂��B����Đ��m�ɂ́h�ǂ�ȕ��ł��n�����t�́h�ł͂Ȃ� �h�ǂ�ȕ��ł����̉t�̂ɕώ������A�t�̉�����t�́h�����������̂ɂȂ�܂��B ����đ��̕���n�����Ηn�����قǂ��̉t�͎̂��ȑ��B���������Ă����܂��B  ���̓����ł��Ƃ�͂�n���͉t���ɂȂ�܂��ˁB  �NjL�F���̉t�̂̌����͂��̉t�̈ȊO�̂ǂ�ȕ��ł��n�������Ƃ��o���Ȃ������� �@�@�@�����Ă��܂��B  |
|
���₢���킹 | �y�����N�C�Y�̔��M��n�I http://quiz-tairiku.com/ |
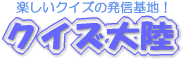

 ���̑̑�
���̑̑� ���̑̑�
���̑̑�