このクイズのヒント
-
ヒント知らないよ
このクイズの参加者(17人)
広告

広告
広告
広告
広告
広告
広告
広告
広告
広告
広告
クイズ大陸関連書籍


|

|
 ツイート
ツイート
|
 中学校理科のクイズ 中学校理科のクイズ
|

|
rocky
なおさん、お早い回答ですね
前者が正解です 後者はそこからは絶対に北には進めませんかね ロック後に私の回答見ていただき是非、私の疑問にお答えいただければうれしいのですが・・・・・ 
rocky
SUEさん、残念
 一応★★★★ですからもう少し・・・・・ 
rocky
PikoPikoサン、相変わらず早いですね
 で? 
rocky
PDJ さんありがとうございます。
私はこの地点というのが無数にあることに気づきました、つまり別解が ロック後、私の解答、解説を見ていただき是非、ご意見をください。 その際はよろしくお願いします 

rocky
チロさん、ありがとうございます
西とか東に進む場合、緯度上を進む場合はその任意の点はあるのですが地学上では地球の最外形上を進むようでその場合は任意の点は存在しません。 ですから「最後に南に10km・・・」ではなく「最後にまっすぐ南下」と言う表示に変えました。
rocky
これが一般的な正解なんですよね



よけいなお世話かも知れませんが、ロック後では意見を述べる場がないと思いますので、
頃合いをみて正解発表、解説をして頂き、すぐにロックしないで皆様の考えをこのスレッド内で聞いてみてはいかがですか  
rocky
SUEさん、ありがとうございます。
そうさせてもらいます。 そのときは是非ご意見をください。 
rocky
そうですね、具体的には?

rocky
ロックする前に公開しますので是非、PDJさんもご意見くださいね
よろしくお願いします 
rocky
ヒナさん、その通りです。
ながさが10kmある建物だとある地点とはいえ不正解ではなく別解です。 ただ、もっとすっきりの解答がありますよ。
rocky
それが本解答ですよ。
ただ、別解があるのでロック前にオープンにしますのできのこ2 さんもご意見ください 

rocky
じゃなくて・・・

rocky
きのこ2さん、ですよ でないと北に進めませんからね


rocky
それが本解答なんですが・・・・・
別解についてあとでちょっと、みなさんと地学の勉強したいと思いますのでよろしく・・・ 

rocky
マキチャンありがとう
 クイズ大陸の歴史とかなり私レベルと比べると学術的な専門的なやり取りを見せられて感動しました。 すべて「すごい」って感じがしました。 まだまだ」私は新参者ですし、ルールさえ理解していませんので勉強になりました。 本当にご親切にありがとうございました。 もともとこのクイズは多分、マキチャンご存知かと思いますが千葉大学名誉教授の多湖 彰名誉教授著著の「頭の体操第1集」のなかの問題なのですが後でですが「問題の表示を変更しないとまずいかな」と気がつきました。そうすれば答えは1つですし、別解も用意しなくていいですよね。 最後の「最後に南に10kmすすむと元に位置に・・・・・」のくだりは「南に10kmではなく南にまっすぐとか南下を続けると元の位置に・・・・」と表記すれば問題はなかったのでしょうけどね。 数年前に「東京から東の○○○kmさきはどこの都市?」というどこかの高校入試を見て答えがかなり北緯に低い(あるいは南緯の高い??)都市だったんで、そのとき「あっやっぱりあのクイズの表示に問題あり」と感じたんです。 もうすでにこういうことに対して皆さん討議されていたんですね。 ただ、私と同じように最近、参加されたひとたちにもできれば考えをきかせてほしいですよね。 マキチャン、本当にご親切にありがとうございました。 勉強になりました  
rocky
ネカルゴさん、私も以前はこの回答を別解答と考えていたのですが、西や東に進むと言うのは緯線上を動くのではなく地球の最外周上を廻ることらしいです。中学校の理科、あるいは高校の地学ではそういうことです。
マキチャンのNo.15の私のコメントを参照ください。
rocky
謎解きちゃん 、正解ですよ



横から失礼します
>西や東に進むと言うのは緯線上を動くのではなく地球の最外周上を廻ることらしいです。 「東京から東の○○○kmさきはどこの都市?」という問題では 示されている情報は始点と方向と距離だけなのでその考え方でいいでしょう 「地面と水平に飛び続けるミサイルを東に発射した」 「東を指さしてロボットにまっすぐ進めと命じた」 これらもその考え方があてはまります しかし「東に進む」という表現には 「意思をもった主体」が東に進み続けるという意味を含みます 真東真東へと方向を修正しながら進む つまり緯度線に沿った移動という解釈のほうが一般的のように思えます >中学校の理科、あるいは高校の地学ではそういうことです。 このように言われるならば もっと明確な根拠を示して欲しいと思います 
rocky
「もっと明確な根拠」??
わかりません。 それで皆さんに意見をいただいるんですよ。 「しかし「東に進む」という表現には 「意思をもった主体」が東に進み続けるという意味を含みます 真東真東へと方向を修正しながら進む」 これが理解できないんです。 

「中学校の理科、あるいは高校の地学ではそういうことです。」
と言い切っておられるので そこを明記した中学高校の教科書・教材をお持ちなのかと思ったのですが いかがなんでしょう? もっと説明すると 人間には何も目印ない場所をまっすぐ進む能力はありません rockyさん が実際何も無い荒野を歩くことを想像してみてください 磁石とかGPSとか、あるいは太陽・星を計測して 自分の向いてる方向をこまめに確認しつつ進まれるでしょう それが「東に進む」の現実的なイメージだと思います 
rocky
永久駆動さん、クイズの範囲で物事考えませんか。
実際にどこかの私立高校の入試模擬試験で目にしました。 そのときに東に・・・というとどこどこの東というと経線を直角にまっすぐ(もっとも地球は球面ですからまっすぐという表現に問題ありといわれそうですが・・・・)となると地球の最外形なんだなあと思ったんですが、この考え方はおかしいですか。 それでオリジナルの問題は「最後に南ますに10km進むと・・・・」とあったのでそこを10kmと書かないで「まっすぐ南下すると・・・」と表現を変えたわけです。 それなら答えはひとつで無数の別解を必要ないですよね。 ただそれだけです。 皆さんはどう考えられますでしょうか、聞いてみたいですね。 

>実際にどこかの私立高校の入試模擬試験で目にしました。
もちろん知ってます もう一度その問題文を読みなおしてみてください はっきりいって表現上ギリギリセーフという問題なんです 「東京から“東の”○○○km“先は”どこの都市?」 “東の先は”という表現がかなり曲者であることを理解してください “東に○○○km進む”とは違うのです 
rocky
なーるほど、よくわかりました
ようは磁石をもって東に東に進むと結局、緯度上を歩くというわけですね ところがひとっとびに東の先○○○kmですと地球の最外形を・・・・ということですね 表示の仕方を気をつけなければいけませんね だとすると問題にも「磁石をもって・・・」を付け加えると問題ないかもしれませんね  ヒミツ


私も横から口を出させていただきます。
>ある場所から北に10km進み 北の定義はどうなのですか?子午線上を北に進むことを意味しているのですか? 子午線は大円(地球の最外周上?の言葉の意味がもう1つ?なので)ですので 問題ないとしても、地理上の特異点、例えば北極点の場合どちらの方を向いても 南で北、東、西はありません。(南極点も同様)地学的にはどのように考えれば 良いのでしょうか?(北極点からは出発できないのでしょうか?) この特異点の考え方で答えが変わる可能性は無いのでしょうか? >次に西に10km進みました。 西の定義はどのように考えておられるのでしょうか? 北に向いて90°左の定義であるなら移動中に常に西に行くように微調整が必要 (経線上の移動)になると思います。それでなければ極端な話一歩踏み出した瞬間 に条件の”西に”から外れることになります。 この問題出題の意図を伝えるには出題文を多少修正したほうが良いと思われます。 例えば 「ある地点から北の方向にまっすぐ10km進み、次にその地点の西の方向に10km 進み、最後にそこから南の方向にまっすぐ進むと最初の地点に戻りました」 といった文なら如何でしょうか? 
rocky
そうですね、最後は10kmと言わないほうがいいですね
問題文も最後の10kmは表示せず南下という言葉を使ったんですけどね・・・・ 

私の考え
東へ=大円で回る 東へ行くとUSAでなく、南米に行く。 問題文の微妙な書き方によってどう考えるか異なりますので、私の一般見解を。 >人間には何も目印ない場所をまっすぐ進む能力はありません 永久駆動さんこのように書いておられますが、これを言ってしまってはすべての「進む」問題は成立しません。まっすぐすすむ能力はあるという前提でなければ、南へも北へも、A地点へ向かうこともできません。 地球が球であるとか、メルカトル図法の地球規模の地図とかグローバルな考えでなく、ある地点で地図を広げて、あるいは磁石を見て、「東に行く」と考えた場合、一度決めた方向に一直線に進むというのが自然ではありませんか。もちろん上下については地球の丸みに沿ってではありますが。 そして一度決めた方向に一直線に進むとどの方向であっても大円で回ることになります。 緯線、経線というのはあとから考えた概念です。そのように緯線に沿って進むというグローバルな考えのほうが不自然に思います。緯線に沿って行くという定義にした時だけ、そのように問題に条件をつける必要が生じると考えます。 
rocky
とにかくクイズが面白くなくなるようなただし書きは書きたくないし、難しいですね。
クイズやパズルは楽しいけど学術的なものになると極めている人にとっては興味深いでしょうけど、一般人にとってはつまらないですからね 


もうひとつ面白いことを考え付きました。
A〜Gの6人が移動します。 Aは西北西へ、Bは北西へ、Cは北北西へ、Dは北へ、Eは北北東へ、Fは北東へ、Gは東北東へ進みます。 1.全員、GPSを見ながら修正しつつ移動します。 2.全員、ただその方向へまっすぐ進みます 結果、 1.全員、時間差があって北極に集まりました。 2.全員、同時に地球の裏側に集まりました。 どちらが自然でしょうか。 

もう問題とは離れて別スレを立てたほうがいいかも
とりあえずこうゆう議論は有意義で面白いです 他の方も思ったことを書いてみましょう 悪いようにはしません(多分) >「東に行く」と考えた場合一度決めた方向に一直線に進むというのが自然ではありませんか。 かなり不自然だと思えます 海を船で移動する場合や 陸地でもなだらかな斜面を横断して移動する場合を 想像してみるとわかると思います 非常に不自然で不合理で飛行機じゃないと実現が不可能な移動方法です 弓矢とかミサイルのように「東に発射される」ならそれでいいのですが 「東に進む」は緯度線移動が 自然です簡単ですイージーですシンプルです 「カムチャッカから東に進んでニュージーランド」は 常識的にやっぱりおかしいのでは? 

>海を船で移動する場合や
>陸地でもなだらかな斜面を横断して移動する場合を >想像してみるとわかると思います >非常に不自然で不合理で飛行機じゃないと実現が不可能な移動方法です このような問題の場合、大円でも緯線沿いでも海、山を考えては何もできません。 単なる球面で考えないと全て無意味な議論になると思います。 「北極点から1mの地点から東へ進む」のは、北極点の周りをぐるぐる回っているだけということでしょうか。 

>24 永久駆動さん 確かに面白い論議だと思います。
過去にも同じような論議がされたことがありましたよね。 (確か”立方体とは”http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=3557) あの時は結論は出ませんでしたが奥深い論議が展開されたと思っています。 さてこの問題ですが私の見解は”どっちもあり”の蝙蝠的意見です。  と、言いますより”定義が不十分である為どちらでも取れる”がより正しいでしょうか。 例えば”右に行く”の場合出発点からその時向いていた方向の右に行く事になります ので大円上になることは明らかです。(移動中の右と考える人はいないでしょう) では”西に行く”の場合はどうなるのか?赤道上で無い限り緯線と大円は同一 では有りませんので判断により違いが出てきて当然だと思います。 >21にも書きましたように”西の定義”を「北に向かって90°左」まではどなたも 同じであろうと思いますが、その後ろに「方向」がつきますとそれは1つの始点を 持った直線となり、大円になると思います。 付かないのであるならば”西は常に北の90°左”ですので緯線上になるのではない でしょうか? (細かい日本語的な表現が正しいかどうかは大目に見てください) この問題の場合どちらとも取れますので(逆に省略することでどちらにも取れる様に 作られたのかもしれませんが)どっちも有りかなと思っています。 (>23のPDJさんの設問もどっちも有りが答えかなと思っています) ただこの問題を見て1つ疑問に思ったこと、>21 に書きました 北極点(南極点)から北(南、東、西)に出発することは出来るのか? これについてどのような見解でしょうか? (rockyさん 本題と離れた事を書き込みましたことお詫びいたします  ) ) 

>単なる球面で考えないと全て無意味な議論になると思います。
私のいいたいのは 言葉の意味を決めるのは「用例」だということ 日本語の「東に進む」がいままでどのように使われてきたか そのたくさんの実例をふまえ 一番妥当な解釈をあてはめるべきなのです あーそういえば立方体の時も説明したけど 理系の人が一番犯しやすい間違いがこれ 「言葉の意味を厳密な定義から求めようとしてしまうこと」 PDJ さんは今お住まいの場所から東に進めますか? 運がよければ東に山がありそれを目標に進めるでしょう でも山についてからはどうします? そんな移動方法は現実にはありえないのです 

単なる球面で考えるかどうかは前提の相違なので議論してもしょうがないようです。
そもそも地球規模でずっと東に進むことは現実ではありえません。 この手の問題ではもともと机上の空論で話をしていると考えなければ、全否定でしょう。 山があるから方向を再確認すると言うのは本来の議論からはずれています。 過去の実例で話をするならば コロンブスは西へ向かってどこに着いたでしょうか スペインを出発して西インド諸島ではなかったですか。 

みなさんはじめまして。
僕も少し思ったことを書かせていただきたいと思います。 僕は、表現の曖昧さから東西はどちらも(緯線or大円)ありかと。 「東に進む」って 1.いつも東の方角を確認しながら進む 2.スタート地点に立ったときに「よし、東はこっちだ」って決めてあとはそっちに向かって進む どっちも考えられるなって思いました。 「東」っていつの東なんでしょうか??? 

PDJさん 議論がかみ合っていないようです
「山や斜面があった場合どうするか」という話をしているのではありません 言葉の意味を決めるのは現在を生きてる私たち全員です じゃあ私達が普通に「東へ進む」と言ったとき 現実的実際的にどんなイメージかな?っとそういう話 前にも書いたかな 私の知ってる数学の先生が国語辞典で「線」をひいて怒った 「線(数学用語)」が「長さをもつもの」と説明してあったからです これは確かに数学の定義として間違いです 点は長さがゼロの線ですから でも言葉の意味を説明する国語辞典の記述としては 「線=長さをもつもの」は正しいのです 点を線とは普通考えないから この「普通考えない」が重要なんです もう一度いいますが 言葉の意味を決めるのは「定義」ではありません「用例」です あとコロンブスは直線移動を意図していません コロンブスの航海こそ 普通「東に進む」「西に進む」が緯度線沿った移動を意味する実例です 

>今回の定義=大円
>今回の用例=緯線 >このようにお考えとしてよいのでしょうか。 まったく違います 大円移動という概念は成立するし それはそれで意味として非常に興味深いです でもその場合は「大円式地球規模方向指定移動」とか 新しく呼び名をつくるべき それからその言葉の定義を明確に決めればいい 「東に進む」という昔から使われてきたありふれた表現に そんな目新しい意味を突然持たせるのは 「言葉の使い方」として間違っていると言っているのです 

お互い確固たる文献的な根拠が示されていないあるいは存在しないので
言葉の定義的な議論はこれ以上進展がないようです。 ただ前に北極点から1mの地点のことを書きましたが、 このような問題も成立するということと解釈します。 ある場所から南に10m進み、次に西に100km進みました。そして、最後に北に10m進むと最初のある地点に戻りました。 さて、こんなことってありえるでしょうか? ********************************************************** 初めの問題に立ち返って 高々10kmの距離を西に進むのに緯線経路を考えるのが現実的でしょうか。 緯線経路であれば赤道上でないかぎり曲線になります。 10kmの距離なら一度決めた方向に直線で進むのが現実的ではありませんか。 そうなると南極点であってもわずかの違いですが同地点には帰ってきません。 このわずかな違いを現実的には同地点だと言われるなら議論になりませんが。 ********************************************************** 初めの問題を見ていて別のことに気づきました。 この議論関係なく南極点なら正解ですね 南下する距離を書いてないのです。 南極点なら初め北に行って次にどんな考えで西に行ってもずーっと南下すれば必ず戻ってくる  。 。

>永久駆動さん ”「東に進む」という昔から使われてきたありふれた表現”
だからいいかげんでどちらとも取れると考えられませんか? >19の 自分の向いてる方向をこまめに確認しつつ進まれるでしょう それが「東に進む」の現実的なイメージだと思います そして >28の 東に山がありそれを目標に進めるでしょう。でも山についてからはどうします? この二つは現実的な「東に進む」方法として妥当なものと思います。 例えば A点から東に進む場合先ず方角を確かめ目標となるB点までまっすぐ進む。 B点では再度方角を確認してC点までまっすぐ進む。 以下これの繰り返し。 ただ移動の途中で不安になった時にその時点で再度方向の確認を行う。 といった方法で私は移動すると思います。(きっと永久駆動さんも同じでは?) さてこの方法で進んだ時、A点からB点は緯線上ではなく大円上を進んでいる訳 なのです。(球の表面の2点を結ぶ線の最短距離は大円上となります) そしてB点で微調整して新しい大円上を進むことになります。 (常時方位を確認して進まない限り緯線上を進むことは赤道以外では有りません) つまり現実的な移動は大円上と緯線上の中間ではないかと思っています。 >PDJさん 「この議論関係なく南極点なら正解ですね」 出題者の rockyさんに聞いて見ないと判りませんがきっとそれが”唯一の正解” として出題されたのだと思います。しかしここで疑問が出てきませんか? どうやって南極点で”北”の方角を決めたのでしょうか?全方向北です。 ある方向を”北”と決めたのなら、おのずと”南、東、西”も決ることになり 南極点から”南”に進むことも出来ることになりませんか? 地理上の特異点”北極点、南極点”はこの問題の場合出発点になりうるのかどうか? これが解明されない限り”南極点”が正解にならないのではないかと思っています。 (>26 に書きました疑問はこの点から出発しております) 

>A点から東に進む場合先ず方角を確かめ目標となるB点までまっすぐ進む。
>B点では再度方角を確認してC点までまっすぐ進む。 >以下これの繰り返し。 スタートした最初は大円上と緯線上の中間といえるけど 繰り返していくと始点を出発点とする大円上移動からは大きく異なっていきますね 基本は緯度線移動で目標を決める毎にやや南へ誤差を生じていく そんな感じになります PDJ さんには いまいち私の主旨が伝わりませんでしたね 「言葉の意味は定義ではなく用例で決まる」とは 別の言い方をすれば 「言葉の意味を理屈で推論しちゃだめ」 PDJ さんはおそらく「東に進む」とう表現から 「その概念として一番正統な意味は何か?」を考えられたと思います 「言葉の意味は頭で考えて推論するものではありません」 私はまずそれを言いたかったのです 頭ではなく耳をつかう たくさんの普通の人に聞いていけばいい みんなは「東に行く」をどんなイメージで使っています? 

もう少し、僕の思ったことを追記させていただきたいと思います。
僕のイメージでは(あくまで僕個人のイメージです)、「東に進む」のスケールが大切ではないかなと。 例えば、東に100メートルと言われたら、僕は目標を決めてそっちに100メートルという、大円のイメージに近いものを想像します。 ところが東に一万キロなんて言われると、どうも想像しづらいというか、大円に沿った移動でも緯線に沿った移動でもどちらも想像してしまいます。 現実的にいって、100メートルの移動ならほとんど同じ場所にたどり着くと考えてしまうのですが、これは日本にいるからではないかなと。 例えば北極圏や南極圏、極端な話では北極点から1メートルだけ離れたところをスタート地点にとると、それぞれでかなり離れたところに到達するので、僕の持っている「東に100メートル」は確実に大円イメージだと言えます。 このことが気になったとともにもう一つ疑問が湧いてきたのが、「例えば北極点近くに住む人がいた場合、その人はどちらをイメージするんだろうか?」ということです。 日本語の辞書での東は「太陽の昇る方向」っていう書き方がされていたと思うのですが、この北極点に近い人たちの辞書にはこうは書かれていないのではないかなと。白夜があったりして困りますからね。太陽の昇る方向=東のイメージは持っていないのではないでしょうか。 これは今議論になっていることとは関係ないかもしれませんが、こういう人たちはひょっとしたら僕たちとは違うイメージを持っているのかもしれません。 

ロシア皇帝 「ハバロフスクまで鉄道を造れ。
モスクワから東へまっすぐ線路を敷くのだ。」 建設大臣 「はっ。ご命令のままに。」 1年後 皇帝 「線路建設は進んでおるか?」 大臣 「はい順調です。やっと中国を突っ切ってベトナムに達しました。」 皇帝 「バ、バカものー!!!!!!」 歴史の中で私の知る限りこのような事件はおきていません えー訂正です 大円移動の例ですが「カムチャッカ」は間違い 「パリから東に進むとニュージーランド」が正解 

>”「東に進む」という昔から使われてきたありふれた表現”
>だからいいかげんでどちらとも取れると考えられませんか? 「東へ進む」という表現は この地面が球体だと知られていなかった時代からあります だから「東に進む」に「大円移動」という意味があることはありえないのです もちろん地球が球体だと知っている現代人の誰かが 『俺は俺の流儀で考える。 俺が「東に進む」といったら「大円移動」のことだ。』と言うのは自由です しかし私はそれも「言葉の使い方」として間違ってると思います。 その人は「大円式移動」とか別な表現を使うべきです。 繰り返しますが「大円移動」は飛行機かミサイルじゃないと実現不可能です 「東を目指したけど地球が丸いため南にずれた」というケースとは 意味的にも実際のルート(大スケール上での)でも異なります 「東京から南米に最短距離で行こうとした人が出発方向を調べたら真東だった」 このケースもありえますが「東に進もうとした」わけではないので意味が異なります SHISHI1さんボムボムさんは大円移動をうまくイメージしきれていないように思われます 大円移動の最大の特徴は 北半球の人が東に進むと赤道を横切ることです 例)東京→南米 パリ→ニュージーランド 「これから東に進みまーす。」と言っていた友人から 「やっと赤道につきました。これから赤道を横断しまーす。」 と連絡が来たら 「お前。何やってんの?」とSHISHI1さんボムボムさんはつっこみませんか? 私なら全力でつっこみます 

>、「例えば北極点近くに住む人がいた場合、
>その人はどちらをイメージするんだろうか?」 面白そうな考察です 極点付近では「東へ」「西へ」という表現は 意味がないので使わないでしょうね でも「東回り」「西回り」という言い方はすると思います 「海岸線に沿って東回りに進もう。」とか 「北極点を西回りで大きく迂回した。」とか 

確かに永久駆動さんのおっしゃる通り、東に進むといって赤道まで達すると突っ込みそうですね。
ただ、地球が丸く今は大円移動法があることも知っているので、こういうことをイメージしたの?という突っ込みも入れそうですが… ただ僕は「東に100メートル進め」と言われたら、一度方角を確認した後目標を探して歩き始めると思います。 これって「北から直角の方向に東という方角があって、そっちに向かって進む」ことをイメージしてると思います。 僕はこういう移動をした人は突っ込まないと思いますが、でもこれは大円移動法であると思います。 方位磁石を持っている場合は、確かに確認しながら100メートル進むという方法をとる人もいると思います。この人にとっては東に進むことは緯線に沿って移動することになっているのだろうと思います。 ただ、方位磁石を持っていない人が、足下に十字に方角が書かれていて、「それを見て東に100メートル進め」と言われた場合、「方位磁石がないから進めません」と言う人はいないんじゃないでしょうか? 前にも書いた通り、日本人にとっては、スケールというのは重要じゃないでしょうか? 僕は、日本人にとって方位磁石を見ながら進むのも、足下の十字に書かれた方角を見て進むのも、生活する上では短距離をどっちの方式で移動しても同じ地点に到達するから、どちらも同じだろうと思っていることに原因があるのだと思います。 

連続での書き込み失礼します。 前に書いた疑問に加えてさらにもう一つ実験してみたいと思ったことがあります。 日本人を北極の近くに連れて行って、その人自身が北極に来ていることを気付かれないようにします。 で、この人に方位磁石を持たせておきます。この状態でこの人に「東に100メートル進め」と言います。 方位磁石を持ちながら進むと北極点付近であるために、すぐに方角がずれていきます。 このとき日本人は「方位磁石が壊れていると思う」のか、「自分が北極の近くにいると思う」のかどちらなんだろうということです。 そしてその結果、東に進むことを継続する場合、どう行動するのだろうか? という実験です。 
rocky
いえーいさん問題よく読んでー
そこからは北へ進めないよ 


ボムボム さんどうも
確かに100mくらいならあまりかわりないですね しかし大円で移動し続ければ 結構早く「あれ?私とんでもない方向に進んでいるのでは?」と気づきますよね 極点付近ならもっと早い 数メートル進んだだけで「えー東に進むってこれでいいの?」と慌てるはず しかしその時「いや東に進むとは大円にそった移動だから絶対これが正しいはず」 と自分に言い聞かせて進み続ける それが「大円移動」です >ただ僕は「東に100メートル進め」と言われたら、 >一度方角を確認した後目標を探して歩き始めると思います。 これはただ単に 「地球が丸いことを計算しなかったので少しずれてしまった緯度線移動」です 「緯度線移動(誤差つき)」以外の何物でもありません 「東に進む」が99.9%「緯度線に沿った移動」を意味することになる大きな理由の1つは 私たちが普段目にする地図の99.9%が 真っ直ぐで水平な緯度線で東西を示しているからです。 ですから私達は普段の生活の中で 無意識に自動的に緯度線の先をイメージして東とか西とかいう言葉を使っているはずです 

永久駆動さん
>39の 「大円移動をうまくイメージしきれていないように思われます」 との事ですが、私の大円移動の基本認識は ”球面上に沿ってまっすぐ進むとそれは大円移動である」ということです。同時に ”赤道以外の緯線上移動は曲線移動である」も有ります。 ある方向に向かってまっすぐ進むことはその距離云々は関係なく大円移動になります。 >35の”つまり現実的な移動は大円上と緯線上の中間ではないかと思っています。” の前に 途中の微調整が0回なら大円上で∞回なら緯線上になりますが、通常有限回の微調整を 行う為これらのどちらでもないと思われます。 の一文を入れておいたほうが良かったのかもしれませんね。 確かに巨視的に見ればこの回数が多くなり大円上よりも緯線上に近いものになるかも しれませんが、微視的に見れば緯線上より大円上に近いものになるかもしれません。 (ボムボムさんの100m東の例などでは大円上ですし) 巨視的に見てこうだから微視的に見るのは間違いと言われるのでしょうか? 又、 >「この地面が球体だと知られていなかった時代からあります だから「東に進む」に「大円移動」という意味があることはありえないのです」 にも少し疑問があります。これでは言葉足らずではないでしょうか? 「東に進む」に「緯線上移動」の意味は有るのでしょうか? 例えば普通の人に「東に○m進む時あなたはどうしますか?」とたずねた時 「常に東を確認しながら曲線状に進む」と答える人が何人いるでしょうか? 特に距離が短い場合には殆ど0だと思います。「東にまっすぐ○m進む」と 答える人が殆どではないでしょうか?これが△kmになると途中で確認をする 人が増え、何百kmになれば殆どの人が途中で確認するでしょう。 この例が正しければ微視的には大円上、巨視的には緯線上に近いとなるのではない でしょうか? 又、昔は東の概念でさえあいまいなもので天測により方位を確認したのでしょうが、 もっと簡単な方法として日の出の方角を東、日没の方向を西としていたと思われます。 とすると春分秋分時には正しいのですが夏至、冬至時には大きく狂ってきます。 (方位磁石も日本では真北でない事を今でもどれだけの人が知っているでしょうか?) この様に現実論で言うならばあいまいでいいかげんな点が多々ある事を地理的な 両極端である”緯線上”と”大円上”の2者択一的に考えるのは疑問だと思います。 >「東に進む」が99.9%「緯度線に沿った移動」を意味することになる大きな理由の1つは 私たちが普段目にする地図の99.9%が 真っ直ぐで水平な緯度線で東西を示しているからです。 ですから私達は普段の生活の中で 無意識に自動的に緯度線の先をイメージして東とか西とかいう言葉を使っているはずです ”そして結果論東とか西の方向にまっすぐ行き大円上の移動をしている” とは考えられませんか? 

「球面上に沿ってまっすぐ進むとそれは大円移動である」
という事実と 「東へ進むとは大円移動を意味するが正しいか」は 全く別の問題です まずそこを分けて考えてください 私が何度も言っているのはそこのことです 「言葉の意味を理屈で推論しちゃだめ」 >確かに巨視的に見ればこの回数が多くなり大円上よりも緯線上に近いものになるかも >しれませんが、微視的に見れば緯線上より大円上に近いものになるかもしれません。 私はミクロマクロの違いではなく 進んだ人間がどう認識しているかの問題だと考えています 北半球にいる人が方位を示す看板を見つける これは便利だと東へ進みます けっこう進んでから今度は地図の看板を見つける 先ほどの地点と今いる地点を確認する 「あれーすこし南に外れてしまったな」 この場合、この人のもつ東という認識は「緯度線の延長」にあり ついうっかり大円移動をしてしまったために 「南に外れた」と結果を判断しています 「東に進む」の意味が「大円移動をする」だというには 東への進行者が次々南側の緯度線を横断していく事を 意識的に確信的に継続的に行う必要があります 特にマクロの大円移動には無謀ともいえる強固な意志が必要です 東を目指しながら赤道を横断していくのですから 「南に外れちゃったよ」では 東への進行者の意識はあくまで緯度線上の移動であり 大円上を進んだのは意図しない結果です 「東に進むが大円移動を意味する」とはいえません 

永久駆動さんのコメントの
No.44 これはただ単に「地球が丸いことを計算しなかったので少しずれてしまった緯度線移動」です。 「緯度線移動(誤差つき)」以外の何物でもありません。 や No.46 「球面上に沿ってまっすぐ進むとそれは大円移動である」 という事実と 「東へ進むとは大円移動を意味するが正しいか」は 全く別の問題です。 この辺りが重要なポイントの気がしてきました。 「東に100m進む」を緯線に沿った移動とイメージしたとしても、結果行動に移すと「大円式移動」に"なってしまう"ということですよね? さらに、「東に進む」という意味を、 「起こした行動ではなく、どう考えて行動しようとしたか?」 ということが大切で、それがすなわち「東に進む」ということの言葉の意味になる。 こういうことでしょうか? 

>「起こした行動ではなく、どう考えて行動しようとしたか?」
今回のテーマは「東に進むの正しい概念は何か?」ではありません 「“東に進む”の意味は大円移動か?」です つまり単純にあるひとつの言葉からの意味の取り方がテーマ そこをPDJ さんもSHISHI1 さんも一番最初に取り違えておられるように思えます お二方ともまず「地球上の一地点から東方向への移動という概念の本質とは・・・」 という考察というか理屈づけから初めてしまった 理系の方のけっこうやってしまう間違いです だから私は何度も何度も 「言葉の意味は定義ではなく用例で決まる」と書いてきたのです では「東に進む」の用例を検証してみましょう 私達が普段耳にする「東」「西」はすべて 緯度線延長上を意味していると私は考えます はっきりした例では ロードマップをピラッと開いて 「東5キロ先にスタンドがある」 ヨーロッパ人が日本を極東(FarEast)と呼んだのも 判り易い例かな 逆に「東」が明確に「大円延長上」の意味とわかる 用例(言葉の使われ方)はあるでしょうか 私が知ってるのはたった一例です rocky さんが引用された 「東京から東の○○○kmさきはどこの都市?」 この問題だけ 

私も東に何キロ移動するといったら、緯線に沿って移動するものだとばかり思っていました。多くの人はそう思うのではないでしょうか?普通、世界地図を頭に描き、東京の東に東に移動したらどこに着くかと問われたら、アメリカ合衆国と答える人が多いのではないかと思います。それは、メルカトール図法の地図を頭に描き、その緯線に沿って、右へ移動するからだと思います。普通、多くの人が、世界地図を頭に描くとき、地球儀でなく、普段見慣れているこの地図を頭に浮かべるのではないでしょうか。
多くの人が思っているから正しいとは限りませんが。 私も、この問題に数年前出会い、なるほど、東京の東に進むと南米に行くと考える人もいるのかと思いました。確かに常に東京からの東を維持していれば南米に行くなあと思いました。 そしてこのとき、この次のように思いました。 普通はこうだけどほんとはこうなんだ ということって世の中にあると思います。 たとえば、黒板にチョークで1本の線を引き、または、紙の上にペンで1本の線を引き ここに1本の線があります。というと、正しくは1本の線ではないという人がいるのです。人間の目に見える以上、それは面であり、線というのはその両側の境目だから、それは2本の線だ。という人がいるのです。学問的には正しいかもしれませんが、普通は1本の線ではないでしょうか? 私は、東京の東へ何キロ先へ移動すると南米に着くというのを聞くと、どうしても このように、普通はそうかもしれないが、ほんとは、学問的には違うんだよね。というように聞こえてしまいます。 普通は、東へ何キロ移動するといえば、緯線に沿って移動するのではないでしょうか。学問的には違うのかもしれませんが。 

通常、東や西に移動といったら磁石やコンパスを持って動くわけですから緯線上に沿ってですよね。
そして東(西)に○○○km先といったら経線に対しそのまま直角(90°)に(球面だから表現が不適当かもしれませんが)した線上にあると考えていいということですよね。 ここまで皆さんに議論していただくとはすごいですね。 以前からスッキリしなかったことが他にもたくさんあるかもしれませんね。 

何か微妙な所ですれ違いがあるような気がしていたのですがやはりあったみたいです。
>46で分けて考えるとの事ですから分けて考えてみましょう。 基本的に永久駆動さんが仰っているのは「言葉の意味」と「その言葉に対する認識」 の問題ではないでしょうか? それでしたら殆どの日本人は「東に進む」の認識は緯線上移動でしょう。 (例えばグリーンランドの人はどう思っているのかは判りません。なぜなら グリーンランドの地図は緯線は直線で無いみたいですから。 wiki先生の”グリーンランド”に乗っている地図とhttp://www.greenland.com/から) しかし今まで私が言っていたのはその行動の結果なのです。 認識として緯線上の移動だとしても大円上の移動になっている可能性があり 結果論として緯線上の移動にはなっていない可能性が高いと考えられるからです。 永久駆動さんもせっかく分けたのですから「東に向かって進んだ時に何処に着くのか」 についても考えてみてください。 rockyさん 「考えていいということですよね。」についてですが、 「その様にも考えられる」とは言えますが、「そうだ」とは言えません。 その用語を使った人がどの様に考えどの様にその言葉を使ったかが問題で 「大円移動」の認識の無い人が使った場合にはやはり緯線上移動を考えて 使われていると思います。(しかし突っ込みは入れれますね) 例に出された文章だけではどちらとも取れないと思います。(引っ掛け問題の 部類に入るでしょう) 最低「東の方向に真直ぐと」と書かれない限り大円上と決め付けるのは早計では 無いでしょうか? (しかしそれでも緯線上を認識されて使用されている可能性はあります) この問題の場合は「大円上」を意図されて出題されていますので表現方法は別にして 「大円上」移動にて考えるべきであると思いますが。 

>「東に向かって進んだ時に何処に着くのか」
>についても考えてみてください。 No.33 で私はこう書いています >大円移動という概念は成立するし >それはそれで意味として非常に興味深いです 地球上の移動に関する考察は私も興味深いテーマだと思います ただ今回は論点が明らかに違うので 議論におつきあいするのを泣いて回避しました 「東に進む」の意味をどう解釈するかという議論で 「本人が意図せず大円上を進む場合もある」も 論点が明らかに外れていると思います ただ1点だけ書くと 地球上の2点を最短距離で結ぶ大円移動は 一見とても合理的なようですが 実際に地図のない場所を移動するケースを考えると とんでもなく非合理です 今あなたは北半球の砂漠を旅しています あるのは方位磁石だけ オアシスAから東を目指し大円上を移動して オアシスBに到着したとします 大円移動ですから最短距離を通ったことになります 一見すると最も合理的な移動をしたように思えます でもオアシスAに帰ろうとして・・・・あれ?となりますね 出発すべき方向がわかりません また途中で砂嵐に出会ってしまい来た方向・進んでた方向が わからなくなると即遭難です 方位磁石を持って特定の方位 例えば「東南東」をキープして進んでいたのなら 引き返すのも簡単「西北西」です 砂嵐がきてもまったく困りません 航海の場合も同じことがいえます 実際の大円移動はこのように非効率で非合理で非現実的です もちろん詳細な地図とかGPSがありコースを計算して進めば 決まった目的地まで最短距離、つまり大円で行くことは可能です でもそれは「東に進む」とはまったく別な話になります 

永久駆動さんのおっしゃる「言葉の意味を用例で決める」には大いに賛成です。
ただ、同じ単語で専門用語も存在した場合は区別する必要があると思います。 物理の「仕事」という用語と、日常生活で使う「仕事」とか。 もし「東」という専門用語が存在すれば、それとは分けて考える必要があると思います。 今回は日常生活の「東」ということで問題ないと思いますが。 >ロードマップをピラッと開いて「東5キロ先にスタンドがある」 >ヨーロッパ人が日本を極東(FarEast)と呼んだ の用例から感じる僕の「東に進む」の印象は「地図の右に向かって進む」です。 これが「緯線に沿った移動を説明している」ということとの間に飛躍があると思います。 今までの用例を見て僕がしっくりきているのは「東=地図の右」ということです。右左に緯線が無くても、です。 どうしてもこのギャップが拭いきれないんです。 

>永久駆動さん
この論議は元々 >西や東に進むと言うのは緯線上を動くのではなく地球の最外周上を廻ることらしいです。 に対して「東に進む」が緯線上移動なのか大円上移動なのかについて始めたものだと 思っておりました。(>18でそう提起されております) この問題提起であるなら「東へ進む」の意味、認識の問題なのか進んだ結果論の 問題なのかは不明ではないでしょうか? 確かに認識上は>53で ボムボムさん が仰っていられるように 北に向かって右(東の定義?)≒地図の横線(普通直線)上≒緯線上移動 と認識している日本人が殆どでしょうが、(グリーンランド人は?) 移動した結果は果して認識と同一と言えるのでしょうか?(私は?と思っています) そして現実的に大円上の移動についてですが、 例えば太平洋航路や長距離の飛行機の場合大円上に近い航路を現在は取っている例は 多々あると思います。(実際航海した事が無いので) 仰っておられるような航路は短距離の場合や一昔(?)前の航法ならその通りでしょう。 (”大圏コース”で調べて見てください。あと”太平洋”などを入れますと遠洋航海 の場合には常識的な航路であるかのように書かれています) 但しこれは2点間を結ぶ最短距離だからで、この問題のように「東へ行く」場合 では有りませんが。 又、大圏コースは難しい計算で算出でき、計算ソフトもあるみたいですよ 

SHISHI1 さんどうも
私はもうだいたい書きたい事はかいちゃったので 繰り返しになるだけなので簡単に >「東に進む」が緯線上移動なのか大円上移動なのかについて始めたものだと >思っておりました そのとおりです 「東に進む」という言葉の意味をどうとらえるか?ですね 「結果論」とは 「本人が意図せず大円上を進む場合もある」ですね 言葉の意味とはイコール発言者の意図です 「本人が意図せず」でもう完全にアウトです 今回のテーマとは無関係の話です これでわかっていただけないようですと 再度「定義と用例」の話をさせていただきます >例えば太平洋航路や長距離の飛行機の場合大円上に近い航路を >現在は取っている例は多々あると思います。 はいもちろん知ってます 下の記述はそれを頭において書いてます >もちろん詳細な地図とかGPSがありコースを計算して進めば ボムボムさんどうも >今までの用例を見て僕がしっくりきているのは「東=地図の右」ということです。 >右左に緯線が無くても、です。 それでいいと思います 手書きの案内図とかも緯線なんか書きませんが 単純に右が東ですよね あー・・・・・マキチャン さんとrocky さんにもコメントしたかった
rocky
ひで さん、頭の体操、ご苦労様でした
 

私も東に何キロ移動するといったら、緯線に沿って移動するものだとばかり思っていました。多くの人はそう思うのではないでしょうか?普通、世界地図を頭に描き、東京の東に東に移動したらどこに着くかと問われたら、アメリカ合衆国と答える人が多いのではないかと思います。それは、メルカトール図法の地図を頭に描き、その緯線に沿って、右へ移動するからだと思います。普通、多くの人が、世界地図を頭に描くとき、地球儀でなく、普段見慣れているこの地図を頭に浮かべるのではないでしょうか。
多くの人が思っているから正しいとは限り>39の 「大円移動をうまくイメージしきれていないように思われます」 との事ですが、私の大円移動の基本認識は ”球面上に沿ってまっすぐ進むとそれは大円移動である」ということです。同時に ”赤道以外の緯線上移動は曲線移動である」も有ります。 ある方向に向かってまっすぐ進むことはその距離云々は関係なく大円移動になります。 >35の”つまり現実的な移動は大円上と緯線上の中間ではないかと思っています。” の前に 途中の微調整が0回なら大円上で∞回なら緯線上になりますが、通常有限回の微調整を 行う為これらのどちらでもないと思われます。 の一文を入れておいたほうが良かったのかもしれませんね。 確かに巨視的に見ればこの回数が多くなり大円上よりも緯線上に近いものになるかも しれませんが、微視的に見れば緯線上より大円上に近いものになるかもしれません。 (ボムボムさんの100m東の例などでは大円上ですし) 巨視的に見てこうだから微視的に見るのは間違いと言われるのでしょうか? 又、 >「この地面が球体だと知られていなかった時代からあります だから「東に進む」に「大円移動」という意味があることはありえないのです」 にも少し疑問があります。これでは言葉足らずではないでしょうか? 「東に進む」に「緯線上移動」の意味は有るのでしょうか? 例えば普通の人に「東に○m進む時あなたはどうしますか?」とたずねた時 「常に東を確認しながら曲線状に進む」と答える人が何人いるでしょうか? 特に距離が短い場合には殆ど0だと思います。「東にまっすぐ○m進む」と 答える人が殆どではないでしょうか?これが△kmになると途中で確認をする 人が増え、何百kmになれば殆どの人が途中で確認するでしょう。 この例が正しければ微視的には大円上、巨視的には緯線上に近いとなるのではない でしょうか? ませんが。 この論議は元々 >西や東に進むと言うのは緯線上を動くのではなく地球の最外周上を廻ることらしいです。 に対して「東に進む」が緯線上移動なのか大円上移動なのかについて始めたものだと 思っておりました。(>18でそう提起されております) この問題提起であるなら「東へ進む」の意味、認識の問題なのか進んだ結果論の 問題なのかは不明ではないでしょうか? 確かに認識上は>53で ボムボムさん が仰っていられるように 北に向かって右(東の定義?)≒地図の横線(普通直線)上≒緯線上移動 と認識している日本人が殆どでしょうが、(グリーンランド人は?) 移動した結果は果して認識と同一と言えるのでしょうか?(私は?と思っています) そして現実的に大円上の移動についてですが、 例えば太平洋航路や長距離の飛行機の場合大円上に近い航路を現在は取っている例は 多々あると思います。(実際航海した事が無いので) 仰っておられるような航路は短距離の場合や一昔(?)前の航法ならその通りでしょう。 (”大圏コース”で調べて見てください。あと”太平洋”などを入れますと遠洋航海 の場合には常識的な航路であるかのように書かれています) 但しこれは2点間を結ぶ最短距離だからで、この問題のように「東へ行く」場合 では有りませんが。 又、大圏コースは難しい計算で算出でき、計算ソフトもあるみたいですよ 私も、この問題に数年前出会い、なるほど、東京の東に進むと南米に行くと考える人もいるのかと思いました。確かに常に東京からの東を維持していれば南米に行くなあと思いました。 そしてこのとき、この次のように思いました。 普通はこうだけどほんとはこうなんだ ということって世の中にあると思います。 たとえば、黒板にチョークで1本の線を引き、または、紙の上にペンで1本の線を引き ここに1本の線があります。というと、正しくは1本の線ではないという人がいるのです。人間の目に見える以上、それは面であり、線というのはその両側の境目だから、それは2本の線だ。という人がいるのです。学問的には正しいかもしれませんが、普通は1本の線ではないでしょうか? 私は、東京の東へ何キロ先へ移動すると南米に着くというのを聞くと、どうしても このように、普通はそうかもしれないが、ほんとは、学問的には違うんだよね。というように聞こえてしまいます。 普通は、東へ何キロ移動するといえば、緯線に沿って移動するのではないでしょうか。学問的には違うのかもしれませんが。 もう少し、僕の思ったことを追記させていただきたいと思います。 僕のイメージでは(あくまで僕個人のイメージです)、「東に進む」のスケールが大切ではないかなと。 例えば、東に100メートルと言われたら、僕は目標を決めてそっちに100メートルという、大円のイメージに近いものを想像します。 ところが東に一万キロなんて言われると、どうも想像しづらいというか、大円に沿った移動でも緯線に沿った移動でもどちらも想像してしまいます。 現実的にいって、100メートルの移動ならほとんど同じ場所にたどり着くと考えてしまうのですが、これは日本にいるからではないかなと。 例えば北極圏や南極圏、極端な話では北極点から1メートルだけ離れたところをスタート地点にとると、それぞれでかなり離れたところに到達するので、僕の持っている「東に100メートル」は確実に大円イメージだと言えます。 このことが気になったとともにもう一つ疑問が湧いてきたのが、「例えば北極点近くに住む人がいた場合、その人はどちらをイメージするんだろうか?」ということです。 日本語の辞書での東は「太陽の昇る方向」っていう書き方がされていたと思うのですが、この北極点に近い人たちの辞書にはこうは書かれていないのではないかなと。白夜があったりして困りますからね。太陽の昇る方向=東のイメージは持っていないのではないでしょうか。 これは今議論になっていることとは関係ないかもしれませんが、こういう人たちはひょっとしたら僕たちとは違うイメージを持っているのかもしれません。 |
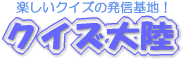

 頭の体操
頭の体操 頭の体操
頭の体操